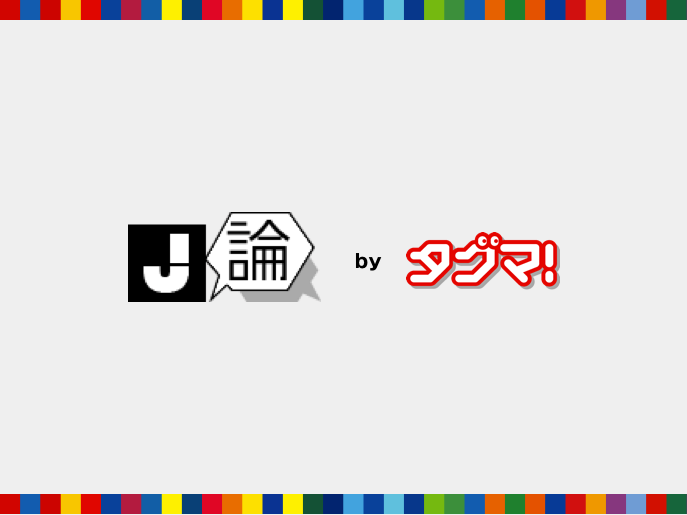昌子、柴崎、金崎、そして小笠原。3連敗に学んで生まれた勝者の気風
開幕3連敗と「暗」の象徴だった鹿島アントラーズは、ここに来ての2連勝で浮上してきた。終了間際で勝ち越す劇的な連勝の原動力に、鹿島の番記者・田中滋が迫った。
▼あまりにも、あまりにも劇的な
出来すぎたシナリオではあるが真実だ。
3連敗で予選敗退に追い詰められていた鹿島アントラーズが広州恒大(中国)、ウェスタンシドニー(豪州)に連勝。次のFCソウル(韓国)とのホームゲームに勝利すれば、一転してグループHを2位で通過できる権利を手にした。
ただの連勝ではないところが、そのドラマ性を高める。広州恒大から奪った決勝点も、ウェスタンシドニーからもぎ取った決勝点も、いずれも90分を過ぎてからの得点。アディショナルタイムに入ってからの勝ち越しゴールだった。
今季は開幕から大きくつまずいた。ACL3連敗を含む公式戦5連敗という最悪の出だし。アジアで勝てないJリーグの象徴のように扱われた時期もあった。そこでもたらされたアディショナルタイムでの2つの勝利は、あまりに劇的なためいくつかの事実を覆い隠してしまっている。じつは、5連敗が止まってから、鹿島はJリーグとACLを合わせても4勝2分と一度も負けていない。連敗の中から選手は学び、成長へと繋げてきたのである。
▼死の組にあらず
一番大きかったのは対戦経験の少なさだ。鹿島がACLに出場するのは2011年以来のこと。ルーキーイヤーだった柴崎岳が1試合途中出場しているが、経験と呼べるかどうかも怪しいもの。いま鹿島の中心となっている多くの若手選手がアジアの舞台を経験したことがなかった。
そのことが相手との力量差を見誤ることに繋がる。つまり、相手をリスペクトし過ぎてしまったのだ。アジアカップに日本代表として参加しながら試合に出ることができなかった昌子源がマークしたのは、そのアジアカップで得点したトミ・ユリッチ。後に昌子は「相手の情報を頭に入れ過ぎた」と振り返っている。ユリッチを気にし過ぎてしまい、本来の自分のプレーを見失ったのだった。
Jリーグであれば未知の相手は少なく、対峙する選手の実力を自分の物差しと比べてプレーを決断することは難しくない。また、たとえ初めての相手でも自分のなかにサンプルがたくさんあれば、正しい対応を相対的に選ぶことができる。しかし、経験のない昌子にはその決断が難しかった。グループステージ第3節・広州恒大戦で、リカルド・グラルに前を向かれた場面では、右利きのグラルに左足のシュートを選択させたものの、見事にコントロールされたシュートはポストの内側に当たりゴールへ入っていった。その反省を生かすことができる2巡目の対戦に入って結果が出始めたのは、偶然ではない。
組み合わせが決まったとき、グループHは”死の組”と呼ばれた。鹿島以外はいずれもファイナルを経験したクラブ、なかでも広州恒大とWSWはチャンピオンクラブだったからだ。そのことも相手へのリスペクトを強めた要因となったことは確かだろう。しかし、化け物揃いかと思われたがふたを開けてみれば予想とは大きく違っていた。
WSWはシーズンが終わりつつあるAリーグで4勝しかできておらず絶不調。FCソウルは豪華だった攻撃陣が相次いで移籍し、ACLの5試合でわずか2得点しかしておらず、Kリーグでも7試合6得点と得点力不足に悩んでいる状況。広州恒大はさすがの攻撃力を有していたが、守備の問題を覆い隠していた破壊的なカウンターは消えつつある。やってやれない相手ではなかった。
戦術的にも、失点の大半を占めていたセットプレーを見直し、試合のペース配分をチーム全体で共有できるようになってきた。特にセットプレーは、相手チームの1番手、2番手の選手ではなく、3番手、4番手の選手にやられていることから全員が責任感を持ってマークする姿勢が植え付けられた。ゴール前で最も声を出す昌子が日本代表で初めて試合を経験できたのも大きい。そこで見た代表選手たちのセットプレーに対する意識の高さ、「おれがこいつにつく!」「じゃあ、おれはこいつ!」と連鎖的にすばやくマークが決まっていく光景は、少なからず鹿島に還元されてきた。
▼揺るぎない空気感
ただし、それだけでは勝てないのがACL。やってやれるようになるには、もう一つの要素が必要だった。チーム随一のテクニシャンである土居聖真は、WSWに勝利した直後、次のように語っている。
「ACLは巧さじゃない。球際とか戦う姿勢が左右する。最初、3連敗しましたけど、やらなきゃいけないというのがわかった」
勝負を左右するメンタル。追い込まれたことで、クールに涼しい顔で勝つよりも、「内容どうこうより勝点3しかいらなかった」(土居)という意識がチーム全体に伝播する。それが、2試合連続でのアディショナルタイムでの決勝弾に繋がり、鬼気迫る思いで戦うことが歓喜を爆発させることに結びついた。
これまでずっと、トニーニョ・セレーゾ監督はチームとしての一体感を大事にチームづくりしてきた。苦しい時間を耐えたチームは、勝てば勝つほど、いい雰囲気と揺るぎない自信に包まれるようになった。
若きリーダーとしてチームを引っ張る柴崎岳。代表での経験を還元する昌子源。あふれる闘志でゴールへ突き進む金崎夢生。復帰早々チームを引き締め勝利に導いた小笠原満男。その他、すべての選手が一体感を持って戦えている。がっちり噛み合った歯車が、まだ回り始めたに過ぎない。
田中滋(たなか・しげる)
1975年東京生まれ。上智大文学部哲学科卒。2008年よりJリーグ公認ファンサイト『J’sGOAL』およびサッカー専門新聞『エル・ゴラッソ』の鹿島アントラーズ担当記者を務める。著書に『鹿島の流儀』(出版芸術社)など。WEBマガジン「GELマガ」も発行している。