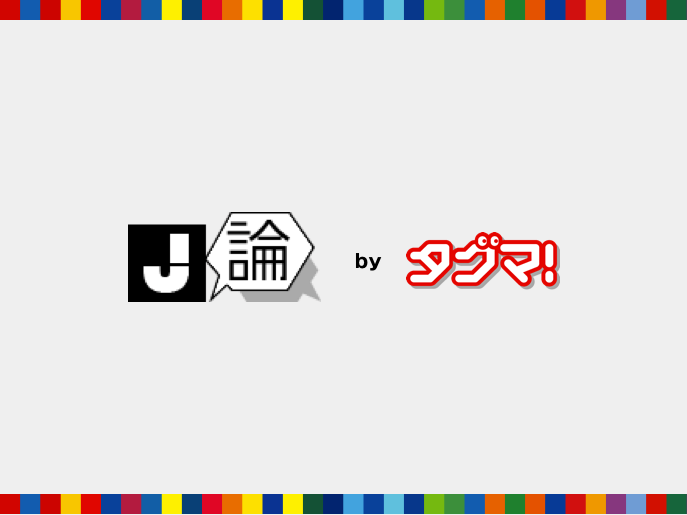“真夏の”高校サッカー選手権。校庭にまかれた思い出の種に思う
普通の都立高校の校庭で始まった、3年生にとっては高校生活の集大成となる大会。そこには何があったのだろうか。

▼真夏の太陽の下、”冬の予選”
圧倒的な攻撃力を発揮した東福岡が17年ぶりに夏の全国高校総体(インターハイ)を制した日から、ちょうど1週間後に当たる8月15日。私は東京都内のある高校へ向かっていた。
都立大山高校。閑静な住宅街に位置するこの学校の校庭を舞台に、高校生にとって1年のラストを飾る大会が幕を開ける。大会名は全国高校サッカー選手権大会東京都大会1次予選。いわゆる”センシュケン”である。
東京は全国の中で最も高体連に所属しているサッカー部が多い都道府県だ。その数は軽く300を超え、わずかに2校が全国への切符を手にすることができる。一部のシード校を除けば、9月末にスタートする都大会へ進出するには、過酷なこの1次予選を勝ち抜かなくてはならない。都大会へ辿り着くために必要な勝利数は最低でも3つ。3日おきに次から次へとやってくる試合をこなし、そのすべてに勝利したチームのみが、秋までサッカーを続けることを許される。
これを灼熱の陽射しが照り付け、競うように蝉が鳴き続ける8月の中旬に行うのだから、選手も保護者も激しい消耗戦を強いられることは想像に難くない。私が赴いた都立大山高校会場の第1試合は1次予選の2回戦。共に1回戦をシードされていた”ホーム”の都立大山と都立葛西工業にとっては、これが大会初戦だった。試合は35分ハーフで行われるので、ハーフタイムも含めて80分後、確実にどちらかの”センシュケン”が幕を閉じることになる。
▼濃密な70分プラスアルファ
都立高校の校庭である。青々とした芝生が生えているはずもない。ピッチは一面の土。特等席は朝礼台の上。この舞台でお互いが”夏の終わり”を懸けて対峙する。実はこの両校、過去2年間は1次予選の初戦で姿を消していた。つまり、双方の3年生にとっては”センシュケン”での初勝利が懸かっているわけだ。果たして「初めて”センシュケン”で勝つ」というのはどんな雰囲気なのか。それがこの会場に足を運んだ一番大きな要因でもあった。
10時ちょうどに試合が始まると、どうやら両者には小さくない実力差が存在していることが分かった。ホームチーム、都立大山が圧倒的に攻め続ける。相手GKの再三繰り出すファインセーブに序盤は苦しめられるも、11分に先制すると、その後も決定機の連続。しかし、追加点は時間の問題に思えた24分に”事件”は突然起きる。ボールをクリアした都立大山のCBと、遅れて飛び込んだ相手FWが交錯。CBはそのまま昏倒してしまった。
チームメイトが、監督やコーチが、そしてご両親が駆け寄るが、安易に動かすことはできない。何とか意識を取り戻すことはできたものの、指導陣の賢明な判断で救急車がピッチの中を横断し、担架でピッチ脇へ運び出されたCBはそのまま搬送されていくことになる。その間、ゲームは10分近く中断。結局、その後は3年生のレフティがハットトリックを達成し、3年生のGKもきっちり相手の攻撃をシャットアウトして、6-0という大差で都立大山が勝利を収めた。だが、様々な意味で非常にインパクトの強い70分間プラスアルファだった。
▼その10年後を思って
試合後、都立大山のキャプテンに話を聞いていると、見るからにお調子者風の子が近くで茶々を入れてきた。彼は3年生で唯一ベンチスタートだった選手だ。試合にも後半途中から出場し、パンチ力のあるシュートも披露していたが、明らかに試合後の方が存在感があった。「ウチはしゃべりたいヤツばっかりなんで」とキャプテン。確かに彼の周りには、「俺にも話を聞け!」と言わんばかりの選手で小さな輪ができている。そんな状況下でハキハキと話してくれたキャプテンはFWで先発出場していたものの、”事件”の後はCBとしてプレー。どうやら大会直前まではディフェンスをやっていたらしく、後半に大量点を奪えた理由を聞かれて「俺がFWじゃなくなったってことですかね」とニヤリと笑うと、周りの仲間も大爆笑。やはりチームには”センシュケン”初勝利の喜びに満ち溢れている雰囲気が間違いなくあった。
監督にお話をうかがったところ、「私はここに来て3年目なんですけれど、私が来た時は紅白戦も組めない人数しかいなかったので、1つ1つチームと学校生活を作り直して、やっと3年経ってこういう風に選手が集まってきたんです。選手権は3年生の大会なので頑張って欲しいですね」とのこと。続けて「我々にとって”センシュケン”は夏の大会と言えますね」と笑った横顔が印象的だった。
ちなみに、この監督とのやり取りは2試合目のハーフタイム中に行われたもの。監督自身が”センシュケン”初勝利の余韻に浸る間もなく直後の試合の主審を担当していたため、「ハーフタイムまで待ってもらえますか?」というお願いを受けて、そのタイミングでのインタビューとなったのだ。今回から埼玉スタジアム2002へ舞台を移す全国大会の決勝は遥か5カ月後。それでも、東京の片隅にある真夏の校庭には、高校生なら誰もが憧れる”センシュケン”が確かに存在していた。
全部で254試合。その数と同じ254チームに”夏の終わり”を告げた1次予選の日程がすべて終わった翌日。彼らの結果が気になって、東京都サッカー協会のホームページを開いた。そこには彼ら、都立大山が決勝まで進みながら、最後は0-5というスコアで敗れた事実が、文字列として無機質に記載されていた。
「少ないながら3年生で頑張ってきたので、もっと一緒にサッカーをやりたいと思います」と話してくれたキャプテンは涙を流しただろうか。2回戦の主役を張ったレフティは躍動しただろうか。ゴールマウスを任された守護神は最後まで折れずに立ち向かっただろうか。お調子者風のアイツは試合に出られただろうか。何より、救急車で搬送されたCBはピッチに帰ってこられていたのだろうか。当然ながら文字列からそこまでは読み取れなかったが、それでも1週間前に砂埃舞うグラウンドで目にした彼らの雄姿は鮮明に蘇る。10年後も私が真夏の”センシュケン”を取材する機会に恵まれていたなら、間違いなくあの日の彼らのことを思い出すはずだ。
そして10年後の蒸し暑い夏の夜、あの5人の3年生が全員揃い、真夏の”センシュケン”の思い出を語り合いながらビールグラスを傾けていたなら、きっと彼らにとってそれ以上に幸せなことはないだろう。
土屋 雅史(つちや・まさし)
1979年生まれ、群馬県出身。群馬県立高崎高校3年で全国高校総体でベスト8に入り、大会優秀選手に選出される。早稲田大学法学部卒業後、2003年に株式会社ジェイ・スポーツへ入社。同社の看板番組「WORLD SOCCER NEWS 『Foot!』」のスタッフを経て、現在はJリーグ中継プロデューサーを務める。近著に『メッシはマラドーナを超えられるか』(亘崇詞氏との共著・中公新書ラクレ)。