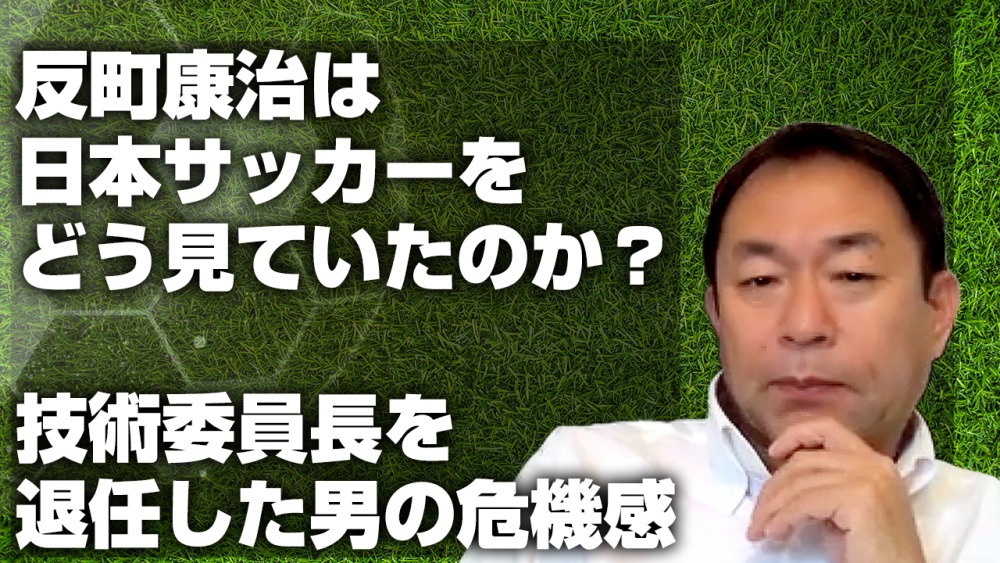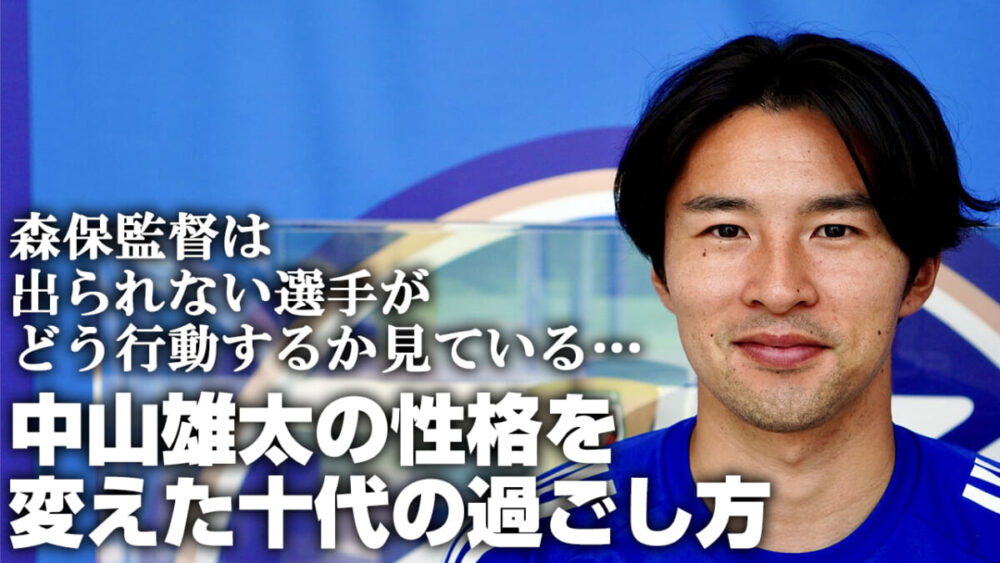解任を伝えるのが一番しんどい…鹿島アントラーズ・鈴木満が語る強化責任者の仕事【サッカー、ときどきごはん】
30年を超えるJリーグの歴史上
三連覇を達成したのは鹿島アントラーズだけ
これまで鹿島は数多くの名選手を輩出し続け
彼らは日本代表や海外へと旅立っていったリーグがスタートしたときはコーチとして
その後は強化責任者としてチームを支え
鹿島の歴史をつぶさに見てきた
鈴木満に鹿島の歴史とオススメのレストランを聞いた
■「選手層は厚すぎず薄すぎず」が大事
鹿島アントラーズはJリーグの歴史の中でただ1チームだけ三連覇しています。ですが、私の中では1996年に初めて優勝して、1998年にも優勝したのですが、1997年も間違いなくJ1で一番強かったと思っているんです(通算勝点は鹿島が68点、ジュビロ磐田が66点)。でもチャンピオンシップで負けてしまった。本当はあそこで三連覇できたと思っています。
2000年は三冠を達成して、2001年もリーグ優勝しました。2002年までは本山雅志や小笠原満男、中田浩二、曽ケ端準、柳沢敦と日本代表の選手が揃っていました。鹿島には若くていい選手が次々に加入してくれたんです。選手の編成を考えると、今いる選手をいかに伸ばすかというところも大事じゃないですか。せっかくいい素材を取ってきて、そこに蓋をしちゃいけない、伸びしろを潰しちゃいけないということを考えてました。
「選手層は厚すぎず薄すぎず」という加減がすごく大事で、そういうことをちゃんとやってきました。だから、選手がみんな代表まで行ってくれてた。そしてそういう編成も大学や高校に評価してもらえたから、鹿島に選手を行かせてくれるようにもなったんですよ。選手も鹿島に行ったら成長させてくれるという思いで来てくれたし。そういう意味でスカウトは手腕を発揮してくれました。鹿島がいい選手を取れたのはそういう理由ですよ。
でもやっぱりみんな海外志向が強くなって、2003年に柳沢がサンプドリア(イタリア)に行き、2005年には中田がマルセイユ(フランス)、2006年には小笠原がメッシーナ(イタリア)に行ってしまいました。
2000年に就任したトニーニョ・セレーゾも、6年間指揮していて、やはり変化が必要なときになりました。それで2006年にパウロ・アウトゥオリ監督に来てもらったんです。そのときに内田篤人も入ってきました。
篤人は抜群のスピードだったりテクニックだったりがあったわけじゃなかったんですよ。ソツなくなんでもできるクレバーな選手だったけど、強烈な武器がある感じでもなかったんです。1年経てば活躍してくれそうだと思っていたんですけど、監督がシーズン前の合宿で篤人を2、3週間見て、「今シーズンの右サイドバックはこの選手で行きたい」と言い始めたんです。だから鹿島始まって以来初めての高卒ルーキーで開幕スタメンでした。
アウトゥオリ監督は最初、強烈な監督でしたね。ただ話していると人間的にはしっかりしている人だということが分かってきました。日本の国民性や社会性のこともだんだん理解してくれるようになって、シーズン後半はいい感じになってきたので、本当はもう一年やってほしかったんです。
でも編成の部分や環境面で細かいところが折り合わなかったり、アウトゥオリ監督はなかなか同じクラブにずっといられるタイプの人でもなかったりしたので、ずいぶん話し合ったんですけど、最後は自分から辞めるということになりました。
クラブとしてはアウトゥオリ監督でもう1年と思っていろいろな準備もしていたんです。けれど、シーズンが終わる1週間前ぐらいに「辞める」という話になったものだから、もうバタバタで。それで2006年12月の終わりぐらいに、2007年シーズンからオズワルド・オリヴェイラ監督でいくことになりました。
2000年までの鹿島の監督は、ジーコの推薦で決まっていましたね。ジーコが「この監督でどうだ」と言ってくれたのがジョアン・カルロスだったり、ゼ・マリオ、トニーニョ・セレーゾだったんです。
その監督がどんなサッカーをするかというより、ブラジルのスタイルを引き継いでいきたいという考えがあったし、ビッグクラブを率いてビッグネームを指導した経験があって、カリスマ性がないと選手をコントロールできないという思いがあったので、そういう人を推薦してもらっていました。それに若手を鍛えるのが得意な監督ばかりだったんですよ。特にセレーゾ監督は三部練習までやっていましたね。鍛えるし、使うし、だから若い選手が伸びました。
でも2002年日韓ワールドカップの後にジーコが日本代表の監督になってからは、自分たちで見つけてこなければならなくなりました。それでも今までと同じ方針で選んでいたんです。アウトゥオリ監督は2005年にサンパウロ(ブラジル)を率いて、オリヴェイラ監督も2000年にコリンチャンス(ブラジル)で世界クラブ選手権に優勝していました。
オリヴェイラ監督が就任した2007年は最初5試合勝ちなし、2連敗してから3分けでしたよね。ヤマザキナビスコカップ(現ルヴァンカップ)も初戦でアウェイのアルビレックス新潟に負けて、3戦目はホームでヴァンフォーレ甲府に負けたものだから、このときは怒ったサポーターがバスを止めてね。
サポーターに囲まれたり、スタンドに居残られることになって、サポーターの代表を呼んでいろいろ話をしました。サポーターと話をするのはそのときだけじゃなくて何回かありましたよ。そのころの鹿島は2002年にヤマザキナビスコカップ獲って、そこから4年間タイトルがないという、それまでの鹿島で一番タイトルを獲っていないときだったんです。
ただ、2007年は世代交代が進んだ年で、興梠慎三のような若い選手が育ってきてたので、監督と選手をアジャストさせればどうにかなると思っていたんですよ。あとはそれがどれくらい早くできるかということが課題でした。
オリヴェイラ監督は一番最初のミーティングで映像を見せたんです。攻めているときにボールを取られたら、FWはその瞬間に切り替えてプレスバックし、前線でボールを奪いまた攻めるというシーンを編集した映像でした。
そして「自分のサッカーの肝はこの攻守の切り替え。ボールを奪い返して、早く前にパスを出す。だからボールを持ったら一番最初にトップを見る」と説明したんです。トレーニングはその切り替えとトップを見るということを意識していて、そんなに珍しい練習をするわけじゃないんだけど、ある程度パターン化されていましたね。
GKがボールを取ったらすぐに2トップが動き出して、そこに投げるなり蹴るという練習からです。そして試合でも最初の1、2カ月は、極端にそればっかりやっていました。でもね、試合ではそんなの普通、繋がらないですよ。周りからは「鹿島は放り込み」をするようになったと思われていました。
選手はせっかく取ったボールを取られちゃうから、きちんと繋ぎたいと思っていました。最初はそこで監督と選手がぶつかりましたね。でも監督は「いいから言うとおりにやれ」と折れなかったんです。そのころが一番気を揉んでいました。
そうすると、だんだん選手も慣れてきて動きが速くなってきた。だけど相手も鹿島の動きが分かってパッと引くようになったんです。そうやってスペースができるようになったのを見て、監督が「近くにいる選手を使ってボールをつないでいい」というようにプレーを解禁したんですよ。そこから普通のサッカーをやるようになりました。
戦術的に特別なことをやっているわけじゃないし、モダンなサッカーという感じでもないけど、最初に前、そこがダメだったら横、それもダメだったら後ろという優先順位の意識付けが出来たことがよかったと思いますね。
そういう意識になって練習していくと、早く前にボールを付けられるようになって、そこからの三連覇だったんですよ。もちろん当時はベンチまで含めると16人だったんですが、年代別も含めれば全員が代表経験者という選手層でしたからね。
それなのに最初は非常に苦しかったのは、シーズン前に野沢拓也がケガをして中盤が組み立てられなくなったからでした。けれど、野沢が復帰してから負けなくなりました。選手が揃って、オリヴェイラ監督が選手の特徴をつかんで、選手も監督のやり方を理解してかみ合い始めた4月以降は白星が先行するようになりました。そして三連覇することが出来たんです。
ただ2007年は、最終戦で鹿島が勝っても首位の浦和が引き分け以下でないと逆転できませんでした。その浦和の相手は最下位の横浜FCだったんです。それでも、その前の節で浦和とのアウェイゲームがあって、そこでは2人退場者を出しながら勝ってたんですよ。それで「もしかしたらこれは優勝できるんじゃないか」と思っていました。
最終節、試合中はすべての情報を遮断しようということになっていました。観客の反応で分かるのもよくないと思って、サポーターにも呼びかけていました。
僕はあの試合、ソシオ席の端にある強化部の席に座ってました。すると隣の座ってる人がチラチラと影で携帯を見ながら「ヤバい」と小声で言ったんです。「浦和が勝っててヤバいのか、負けてて鹿島が優勝しそうだからヤバいのか、どっちなんだよ」とヤキモキしたんですけど、とにかく見ませんでした。
そうしたら後半のロスタイム(アディショナルタイム)、誰かがオリヴェイラ監督に「浦和が負けている」ということを伝えたんです。そうしたらオリヴェイラ監督は「負けている」を「負けた」と勘違いして、まだ浦和の試合が続いているのに喜んで走り出しちゃったんですよ。
自分たちの試合が終わって、電光掲示板に浦和と横浜FCの試合が映し出されて、監督はまだ試合が続いていると分かったみたいです。あとでスタッフに「嘘を教えるな。終わったって言ったから一人で走り回って恥ずかしかったじゃないか」と文句を言っていましたね(笑)。
2011年でオリヴェイラ監督との契約が終わって、2012年は1年間ジョルジーニョ監督にお願いしたんですけど、そのころは小笠原たちの世代から昌子源、柴崎岳、土居聖真たちの世代に交代する時期だったんです。そこで世代交代が得意なセレーゾ監督に2013年からもう一度お願いしたんです。「どんどん練習させて、鍛えてやってほしい」って。結局セレーゾ監督は鹿島で3回世代交代させました。
そして2年経った2015年、若手が育ってきたし、まだベテランも元気だったし、この組み合わせで今年は勝てるとセレーゾ監督に言ったんです。でもセレーゾ監督は「あの若手も鍛えればもっと伸びる」と言ってそちらを優先しちゃうんですよ。
それにセレーゾ監督は指示を出しすぎるから選手がその声に敏感になっちゃって、主体性がなくなってきたんです。試合中もずっとタッチラインのギリギリまで出て行って、ずっと声をかけているから。
監督が出しているような指示もピッチの中にベテランがいれば、選手の間で解決してくれるから問題ないんです。選手選考は監督の専権事項だから口出ししないようにしていたんですけど、でもこのときばかりは「今年は勝たなければいけないんだから、将来性を見るのではなくて、いい選手を上から順番に使ってくれ」と申し入れしました。でもなかなか聞いてもらえなくて。
セレーゾ監督とは9年ぐらい一緒に仕事をしてお互いにいろいろわかり合っていたとは思うんです。けれど、これはもう仕方がないと思って石井忠正監督に交代しました。石井監督は選手に主体性を持って自由にプレーさせ、それを後ろからサポートするというタイプだったんで、それまで閉じ込められていた選手の気持ちがパッと放たれて、それでよくなりました。だから2015年のヤマザキナビスコカップに優勝できたし、そこで自信が付いたから2016年のリーグも優勝できました。
■今の鹿島には次の世代を育てる時間がない
2007年の三連覇したぐらいまでは、一度レギュラーになると10年以上活躍してくれていました。だからうまく世代交代の準備をする時間があったんです。たとえば小笠原が30歳になったときに次の世代を育てて、その育てた彼らが30歳ぐらいになったらまた次を育ててというサイクルが出来上がってました。
でも今は選手が海外に出て行くから、在籍期間を4年ぐらいで考えなきゃいけない。だから世代交代の準備が出来ないんです。
移籍での補強は、昔ならピンポイントで足りないポジションだけ、完全にレギュラーを取れそうな選手を取ってくればよかったんです。大岩剛、新井場徹、西大伍とかそういう選手です。でも今は主力になるとすぐに出て行くから次の世代を育てている時間がない。だから監督選びから変えました。
昔は、監督が育てながら自分のサッカーのスタイルと選手をうまく融合させられる時間がありましたけど、今は監督の形に合う選手をできる限り集めて、そこで戦ってもらうという感じになっています。だから監督の選び方も、昔は選手をコントロールできるかどうかという点が大事だったんですが、今は監督のスタイルを重要視して選ぶという形に変わりました。
そして、選手は代表クラスなら22歳ぐらいになると海外に行ってしまうので、そのポジションを埋めるためには下部組織にそういう選手がいないといけない。そのために下部組織のためのスカウトを充実させました。寮を新しく作って安心していろんな地域から来られるようにして、そしてアカデミーからトップまで一貫した体制を作ったんです。
2017年にJリーグはDAZNとの契約金を元に「理念強化配分金」が大幅に増額しましたよね。それを狙いに行ったんですけど2位になった。それでも2位になってその賞金でアカデミーの寮を作ったんです。
そしてアカデミーからユースまでの選手の成長具合を見ながら、足りないポジションを移籍で獲得するというようにしています。それができたのは、鹿島はどんな監督が来てもサッカーの方向性が変わらなかったからでしょうね。
じゃあ鹿島のサッカーはどういうものかというと、ジーコがいたからブラジル流だと思っている人が多いんじゃないかと思うんです。ブラジル人はやはり個人戦術が優れていて、ブラジル流とは彼らの個人戦術とブラジル伝統のサッカーのセオリーの集合体だと思います。それに対してヨーロッパはシステマチックで、そこに選手を当てはめていきますね。
僕は、ポゼッションとプレッシングの中間が一番勝てると思っていました。ポゼッションも出来るけど、守から攻の切り替えが早く、前からのディフェンスもプレッシングも出来る。だから鹿島は基本的に「キーワードを作らない」というのがキーワードだったんです。
キーワードがあると、それが目的になっちゃう。本当は勝つための手段なんですけど、そこにばかり目が行って結局勝てない。だからクラブとして「キーワード」を打ち出したことがないんです。聞かれたときに敢えて言うなら「臨機応変」でしたね。
鹿島の試合を見たいろんな人から「鹿島っぽい」と言われることがありますね。たしかに歴代で同じようなことを目指してきたのかもしれないですけど、言語化していないというか。手段を目指しすぎて、一番の目的にたどり着かないということがないようにしてきたんです。
それは、ジーコが「日本人は同じことをスタートから90分間やろうとし過ぎる」と言われたことにも関係しています。本当だったら試合展開、点差、試合の位置付け、状況によってやり方は変えなければいけないはずでしょう? 「ゲームはそのときどきでコントロールしなきゃいけない。日本のサッカーで一番欠けているのはそこだよ」とジーコに言われてました。そのころに「ドーハの悲劇」があったので、余計に説得力がありました。
そういうことを歴代の選手たちはずっと言われ続けて、そういうのが積み重なって、伝統というか自分たちのスタイルみたいになっている部分はあるかもしれないですね。それからあとは「鹿島の選手はどんな状況でも勝つのは自分たちだと思っている」ということも言われますね。
三連覇の最初の年の2007年もそうだったんですよ。残り9試合で首位の浦和レッズには勝点で10の差を付けられていたんですけど、最後9連勝して優勝したんです。もちろん鹿島が勝ったというのはあるんですけど、浦和が最後の5試合勝てなかったんですよ。
あそこで勝てたのは、それまでに鹿島には優勝経験があったからだと思いますね。やっぱり優勝したら強さは変わるんです。川崎フロンターレも2017年に最終節で鹿島を逆転して優勝したあと、グンと強くなったでしょう?
鹿島は1993年のファーストステージで優勝したことが自信になりました。あのとき僕はコーチだったけど、正直に言えば「真ん中ぐらいになればいいな」と思っていました。ジーコだけは「絶対優勝する」と言っていましたけど、みんなは「まぁ無理だろう」と考えてたんですよね。結局チャンピオンシップで負けたから本当のチャンピオンじゃなかったんですけど、やっぱり優勝というのは自信になりましたよ。
タイトルを獲るというのは山の頂上に立つのと一緒なんです。頂上に行ったことが無いと、どこを登ったらいいか確信が持てないから、こっちに行こう、あっちに行こうと迷っちゃって、なかなか頂上にたどり着けないんです。でも上に立って下を見ると「こういう道があるんだ」というのが分かるし、「意外にこの山も簡単なんだ」と理解することができるんです。
「鹿島アントラーズ」ができたとき、僕たちは周りから「こんな小さなホームタウンで興行がしっかり成り立つのか」「日本リーグ2部から入れてもらって戦力的にもお荷物になるんじゃないか」と、そういう評価をされていたんで、本当に危機感で一杯でしたね。何もないところからのスタートですよ。
でもそのころってJリーグができても、どのクラブもフロントはどんな役割と仕事をしたほうがいいか、誰も分かってなかったんです。そういう意味では横一線のスタートでした。
だからまず「鹿島アントラーズ」というブランドを作らなきゃいけない。あのころはヴェルディ川崎(現・東京ヴェルディ)と横浜マリノス(現・横浜F・マリノス)が大人気クラブで、彼らにいかに追いつくかというのを考えていました。それから世間に「鹿島アントラーズ」を認知してもらわなきゃいけない。
当時、ヴェルディやマリノスの選手はテレビに出たり派手な印象があったので、こっちは純朴な雑草軍団でサッカーしか取り柄が無い、小さな町のプロビンチャがビッグクラブに立ち向かっていくという構図を作って、その中で「鹿島は強い」と思ってもらうという戦略でした。日本人の判官贔屓に訴えるというか、そういうのを利用しながらイメージ作りをしていこうと。
だけど、自分がやっていることが正しいかどうかなんて、それまでプロがなかったんですから分からないんですよ。だからいつも半信半疑です。来ているメディアのみなさんに「他のクラブはどうやっているか」という情報を聞いて、それを整理しながらやってみるという感じでした。
クラブハウスにはいつもサポーターのみんなが来ていましたね。当時、このクラブハウスでチケットを手売りしていたんですよ。今みたいな販売システムなんてないから。試合だけじゃ認知率が上がらないだろうということで、練習も常にオープンで。そうやっていろいろウェルカムじゃないとやっていけない時代でした。
僕たちの時代は全部公開で通用していたという部分もあるし、今はそんなことをやったらダメと言われるのかもしれないし。ただ、サッカーは野球のようにピッチャーが右投げか左投げかで選手が変わってくるなんてことはないから、見せてもいいと思うんですけどね。
だけど今はテクノロジーが発達して、いろんな分析ソフトや映像から詳しく相手のことが分かるようになっているから、やっぱり昔よりは隠さなければいけないという部分も増えたと思います。

■チームが負けたときは「申し訳ない」という気持ちが強かった
三連覇したあの時代、2007年度は鹿島の営業収入が約40億円、あとは浦和だけが80億円と頭一つ抜けてたんですけど、横浜FMが49億円、磐田と名古屋が36億円、G大阪が32億円という規模だったんです。それがだんだん格差が出てきてるのは事実で、2024年度のJ1では鹿島が72億円、浦和が102億円、川崎が85億円なんだけど、福岡と鳥栖は31億円なんですよね。
じゃあ、それが成績の格差に繋がっているかというと、それは広がってないんです。その原因は優勝したクラブでも選手が海外に抜かれていくから。世界のサッカー市場で言うとJリーグよりももっと上のカテゴリーがあるから、そこに選手を取られてしまってなかなか強さを維持できないんですよね。
在籍期間が4年ぐらいになった主力がポンポン抜かれてチームを作り直さなきゃいけない。それが本当の意味で強くなっていけない理由の一つです。
海外のクラブとは経営規模の違いがあって、いい外国籍選手もなかなか取れない。昔在籍したレオナルドやジョルジーニョなんて、今だったら移籍金が100億円、200億円かかるでしょうね。
そうするとスーパーな外国籍選手は取れないし、日本人もトップクラスはクラブに残らないのでなかなか強くなれないです。だからますます、外国籍選手や日本人選手を育てて移籍金でうまく稼いでアカデミーに投資することを考えなきゃいけないんです。だけど、アカデミーにばかり目が行って、ちょっと失敗するだけで勝てなくなるのがJリーグでもあるんで。
今のJリーグではなかなか強さを維持できないのが問題点の一つだということで、強化担当者の教育なんかをしているんですよ。ヨーロッパでの日本人選手の価値も上がってきているので移籍金も取れるようになってきたから、これから改善していかななければいけない点ですね。
※この続きは「森マガ」へ登録すると読むことができます。続きはコチラ