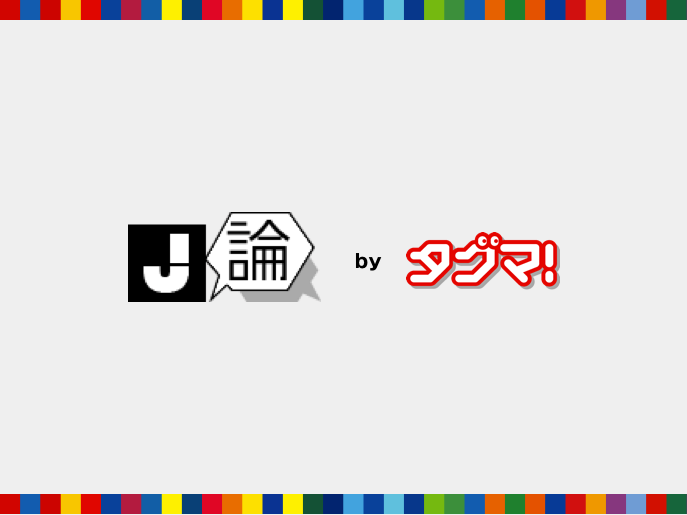日本代表に「テストマッチ」なんて要らない!! サバイバルの4年間だけが日本を強くする
オンとオフの切り替えが弱い日本人のチームである「日本代表」の適切な強化策とは何だろうか。
▼W杯で見えた「建築家の限界」
アギーレの語り口を聞いて、思い出したことがある。
手前味噌で恐縮だけど、2013年5月に行われたブルガリア戦の後に、こんな記事をアップしていた。
「テストマッチ丸出しの試合に意味があるのか?」
http://bylines.news.yahoo.co.jp/shimizuhideto/20130531-00025362/
振り返ると、ザッケローニ監督は「テストマッチ」という言葉をよく使っていた。キリンチャレンジカップなどの記者会見では、「この時期の試合は結果よりも内容を見たい」というコメントをよく聞いた。僕はその手のザックの物言いには常に違和感を覚えていたので、そのモヤモヤを書いたのがこのときの記事だった。
緊張感はあるのだけど、勝負事ではなく、どこか研究所のような類のピリピリ感というか。
もちろん、テストマッチの内容が大事というのはよくわかる。日本代表の場合はなおさらだ。たとえばドイツやスペインといった国なら、限られた世界トップクラブから、すでにある程度の連係や約束事でつながったメンバーを選び出すことができる。しかし、日本はそうはいかない。有力選手が国内外にバラけているので、広く選手を集めて、チーム作りはゼロからやらなければならない。必然、テストしなければならないことは増える。
そうやってチームとしての戦い方を突き詰めるために、メンバーは固定されたが、1試合1試合の「テストマッチ」に真剣に臨んでチーム構築を進めた。対戦相手の監督から、「日本代表はクラブチームのようだ」という賛辞をもらうこともあった。それは内容にこだわってテストマッチを積み重ねたことの産物だろう。
そう思ったので、僕は上記のようなテストマッチの雰囲気をくさす記事を、その後は書かないことにした。メンバーの固定化を批判するメディアも多かったけど、僕はそこにも与しなかった。日本代表はバラバラに選手を集めなければならない。連係のためにはメンバーを固定してテストを重ねるのも仕方のないことではあるし、岡崎慎司を見ても、吉田麻也を見ても、どの選手もテストマッチで何にトライしているのかが、よく伝わってきた。内容にこだわってクラブチームのように成長するさまを、しばらく見守りたいと思った。
だけど実際のところ、『内容が大事』な試合を積み重ねたザックジャパンは、『結果がすべて』のW杯の舞台になって、お互いの意志がバラバラになってしまった。
コートジボワール戦だけを見ても、これがテストマッチならば1-0の状況からもっとラインを高く上げて押し返そうとチャレンジしたはずだが、やはり本番ではリスク回避の意識が強い。耐えよう、耐えようと、「テストマッチ」とは違う意志エネルギーが働いた。
せっかく積み重ねても、これでは意味がない。テストマッチ丸出しの雰囲気が出てしまえば、それはテストマッチにもならない。本番では役に立たないということを痛感した。
あるいはイタリア人のように、もともとの気質として親善試合と公式戦をまるで別人のように戦う習慣があるのなら、話は別かもしれないが、日本人はそうではない。そこまで強烈にオンとオフを切り替えるイメージには慣れていない。本番であたふたと焦る様子が、ただひたすら悔しかった。
▼ヌルい試合は要らない
親善試合に対する考え方は、アギーレとザックでは大きく異なるようだ。メンバー発表会見で、「初戦から『戦う、競争力のあるチーム』を見せたい。そして常に勝利を目指して戦うチームを見せたいと思う」と語るアギーレのコメントには、前任者との違いという意味でインパクトがある。
クラブのように連係するチームを作った建築家、ザックの方向性は決して間違っていない。それは必要なことだ。ただし、そこにはもっと『勝負事』のニュアンスを強調するべきだった。日本人を指導するなら、特に。ただでさえヌルい雰囲気があるキリンチャレンジカップと、『テストマッチ』という言葉の相性が非常に悪かった。
最初にアギーレに望むこと。それは、おそらく彼がやろうとしていること。
それはキリンチャレンジカップを、「負けたら何も意味がない」ほどの厳しい勝負事の場にすること。そして、結果を残せなければどんどん下から突き上げられる『サバイバル』の場にすること。
その中で内容を突き詰めれば、それはW杯であっても”普段通りに”発揮できる力になっているはずだ。
清水 英斗(しみず・ひでと)
1979年12月1日生まれ、岐阜県下呂市出身。プレーヤー目線で試合を切り取るサッカーライター。著書に『日本代表をディープに観戦する25のキーワード』『DF&GK練習メニュー100』(共に池田書店)、『あなたのサッカー観戦力がグンと高まる本』(東邦出版)など。現在も週に1回はボールを蹴っており、海外取材に出かけた際には現地の人たちとサッカーを通じて触れ合うのが最大の楽しみとなっている。