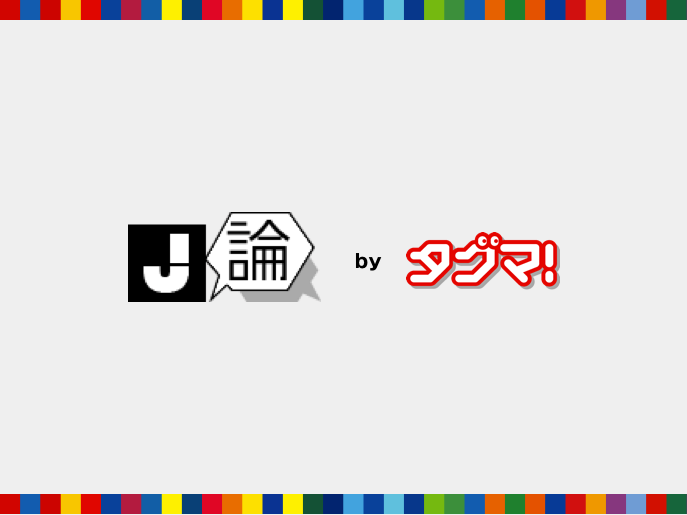ミシャが礎を築き、森保一が幅を加える。CS優勝の源泉は、広島苦難の歴史にあり
チャンピオンシップを1勝1分で制したサンフレッチェ広島にフォーカスし、年間最多勝ち点と年間優勝を達成した最大の要因に紫熊の番記者・中野和也氏が迫った。
▼G大阪の対策を凌駕した”二の手”
内容からすれば、連敗してもおかしくなかった。長谷川健太監督の知的な采配に、サンフレッチェ広島が「完璧に崩した」と実感したシーンを生むことはほとんどなかった。抜擢した長澤駿を中心に、前線からのプレスを徹底し、遠藤保仁にも守備のタスクをいつもよりも多く与えた。
この長谷川戦術を受けて広島は裏を取るどころか、ボランチのラインを超えてボールを運ぶこともできず、サイドに展開してもガンバ大阪のサイドハーフとSBが二人で対応し、決定機を作らせない。第1戦も第2戦も、前半からG大阪が主導権を握ったのは当然の内容だし、先制点が青黒に墜ちたのもまた納得だ。
だがこの戦術は、佐藤寿人が1トップに入り、コンビネーションを強く意識しているときの広島対策。森保一監督は今季、2段ロケットのような戦い方を1年間かけて準備していた。もちろん、浅野拓磨が入ったときの戦術である。
もっともそれは大げさなものではなく、「裏にスピードのある浅野を走らせる」というシンプルなモノ。だが、丁寧にクサビを入れてショートパスを展開して手間暇をかけるスタートの戦術から、一気にロングボールを打ち込んでくる戦い方に変わったとき、守備で臨機応変に対応するのは難しい。特に浅野のようなナチュラルなスピードを抑えることは、現実的には困難だ。
しかも広島の場合、青山敏弘や千葉和彦、森崎和幸や塩谷司など、正確なロングフィードを持つ”クオーターバック”がたくさんいる。前線のジャガー・浅野にとっては、おいしい餌をたくさんくれるタレントが存在するわけで、ボールを誰かが持てば、いつでもスタートは切れる。G大阪にしてみれば、常に裏に対して神経を研ぎ澄ませねばならない。必然的にラインは低くなる。
森保監督にしてみれば、第1戦も第2戦も十分に機能していたG大阪のコンパクトなゾーンを、浅野の投入によって崩壊させたと言っていい。その結果として、ずっと抑え込まれていた青山の躍動が始まり、ドウグラスにもボールが入るようになった。サイドも高い位置が取れるようになり、ますますG大阪のラインは低くなる。75分以降、ペースが広島に移るのも当然の帰結で、第1戦にて清水航平とオ・ジェソクが横に向かったドリブルでせめぎ合ってオの退場劇が生まれるのも、そこにスペースがあったからだ。
▼G大阪に深い傷を負わせた第1戦の同点弾
象徴的なシーンは第1戦の79分、ドウグラスの同点弾である。塩谷がセンターライン付近から放った裏へのパスに浅野が走り込んだ。このとき、GK東口順昭は塩谷のパスをクリアしようと反応し、ゴール前を空ける。だが、浅野の想像を超えたスピードは、日本代表GKの思惑を許さない。ドリブルでGKをかわしたジャガーは、角度のないところから一気にシュートを放った。このボールがポストに当たり、柏好文を経由してドウグラスが決めた。そこまでのG大阪ペースを一変させ、広島に希望を与えた一撃となった。
この場面は、チャンピオンシップを通してG大阪守備陣の心に深い傷を刻み込んだ。浅野のスピードにどう対処していけばいいのか。その対応策を確立させることはできなかった。この若者は、ただ裏を狙って走るだけではない。広島のDNAをしっかりと受け継ぎ、ボールを収めることもフリックもやろうとする。精度は決して高いとは言えないが、やろうとしてくるだけでも、DFにとっては判断の迷いが出る。密着してつぶそうと思っても、強烈なキレを見せて反転されれば、裏を取られて追い付けない。結局、対策としてはラインを深めにとってカバーするしかない。
スタートで佐藤寿人が駆け引きを弄し、交代して浅野が爆発する。コンビネーションを封じる手立ては構築できても、DFが疲弊している時間帯に登場する”浅野ロケット”を完全に止めることは難しい。ましてこのCSには、それに加えて”柏ブースト”も存在した。浅野は優勝を引き寄せる第2戦のゴールをはじめとして2試合で3得点に関与。柏にいたっては、全得点に絡んだ(1得点2アシストを含む)。組織を破壊されたわけではないが、圧巻のスピードでピッチを走り回る広島の野獣たちを、G大阪は止めることができなかった。
▼ペトロヴィッチ監督が築いた礎の上に
ペトロヴィッチ前監督(現・浦和)が整備した広島の戦い方は、高い技術とブレのない判断、そして相手の虚を突く発想力を組み合わせ、洗練の極みを求めたコンビネーション。財産を受け継いだ森保監督は、そこにスピードや強さといった荒々しさも加味した。1990年代後半、久保竜彦の躍動を中心に強烈なカウンターを次々と爆発させた広島の凶悪と言っていいすごみを、洗練に上乗せした広島の幅広さこそ、年間1位の源泉である。
ただ、そうは言っても初戦、1-2とリードされていた状態でG大阪に守り切られてしまえば、結果は逆になっていただろう。確かに数的優位な状況ではあったが、相手に割り切って守ってこられると、崩すことは難しい。G大阪はなりふり構わず、守っていた。ペナルティーエリア内に9人の選手が入ってゴール前を徹底して固めていた。守備への構えは万全だった。
だが、それでも広島はこじ開けた。一つは、1990年代に得意としていたセットプレーからの高さ。もう一つは、前監督がベースを築いたコンビネーション。広島のゴールはいずれも、過去の歴史の中に答えが存在していたバリエーションだ。クラブの伝説的な存在であり、過去も未来も身体の中に染み込ませている森保監督を媒介として、広島が歩いてきた苦難の歴史がチャンピオンシップの勝利を生み出した。僕は、そう信じたい。
中野 和也
1962年3月9日生まれ。長崎県出身。居酒屋・リクルート勤務を経て、1994年からフリーライター。1995年から他の仕事の傍らで広島の取材を始め、1999年からは広島の取材に専念。翌年にはサンフレッチェ専門誌『紫熊倶楽部』を創刊。1999年以降、広島公式戦651試合連続帯同取材を続けており、昨年末には『サンフレッチェ情熱史』(ソルメディア)を上梓。今回の連戦もすべて帯同して心身共に疲れ果てたが、なぜか体重は増えていた。