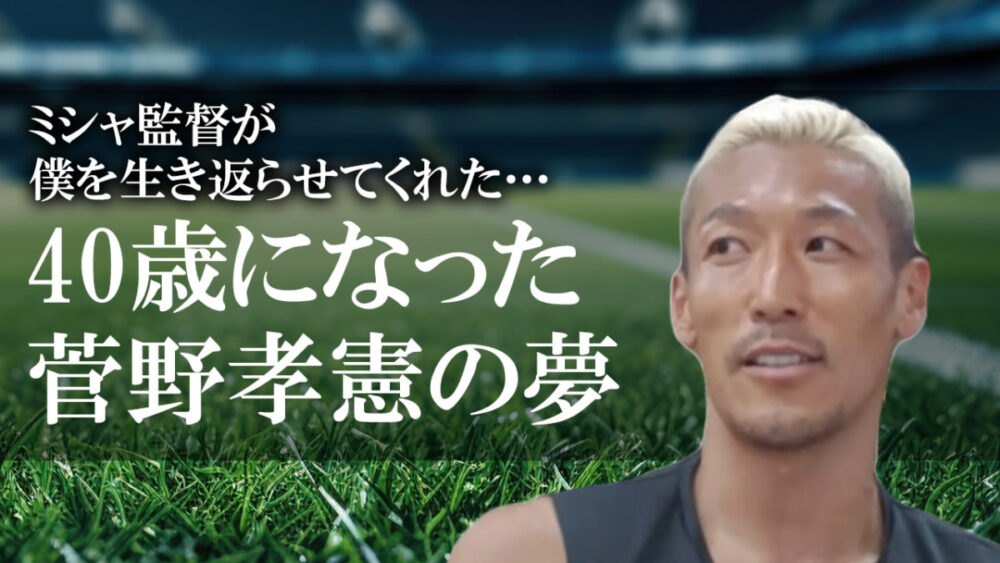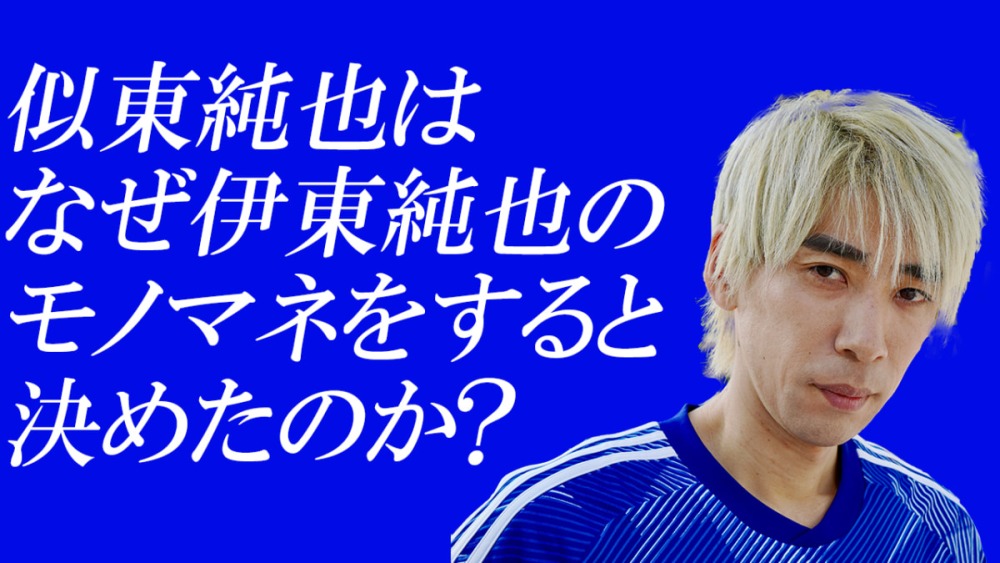4-2-3-1と4-3-3の違いが分かるようになった…今井美桜が取材 で得たものとは?【サッカー、ときどきごはん】
かつては数多くのサッカー番組があった
しかし時代の流れとともに姿を消していってしまった
その中でただ一つ
20年以上Jリーグを放送し続けている番組がある今は各地域にご当地チームを応援するローカル番組が出来た
それでもリーグ全体を応援する老舗番組の価値は変わらない
プライベートでもJリーグに通いつつ番組に出演する
今井美桜に半生とオススメの食べ物を聞いた
■サッカー番組出演前からサッカーは現地観戦派
サッカーは、父が少年団のコーチで、弟がその少年団で真剣に取り組んでいたので、休みのたびに家族みんなで父と弟の試合の応援に行っていました。それに家族旅行があると、旅先でなぜかJリーグの試合を見ていたんですよ。神戸に行ったらヴィッセル神戸の試合を見る、みたいな。今考えると、父は見たい試合があったからそっち方面に家族旅行を計画していたんだと思います。
大学時代はフットサルのサークルに入っていました。高校まではバスケットをやっていたのですが、大学に入ったのでがらりと環境を変えたいと思って。マネージャーじゃなくてプレーヤーです。サッカーとはまた違いますけど、自分でもボールを蹴ってみたいと思ったんです。
フットサルの練習は週1回、NHKのとなりの代々木公園でやっていましたね。大学の中でフットサルの大会があって、それに出たこともありました。でも私は端っこでちょっと球を蹴ってたぐらいです。男子はいろいろなクラブの下部組織出身の人たちや高校選手権に出ていましたという人がいたんですけど、私はとてもそんなレベルではなかったですね。
大学を卒業したのが2020年で、新型コロナウイルスの影響が出始めたときです。卒業式はギリギリできたんですけど、他の大学の友人たちには式自体がなくなった人もいました。卒業旅行はヨーロッパに行ってサッカーを見ようとしていたのですが、結局コロナ禍ということで行けませんでした。
海外には2022年の終わりぐらいから行けるようになったのですが、そのときに行ったのが2022年カタールワールドカップなんですよ。「現地で見るのが一番楽しいし、盛り上がるし、いいな」と思って友達を誘って、0泊3日の弾丸ツアーでした。
本当は日本戦を見てドーハに泊まりたかったんですけど、日本戦のチケットが手に入らなかったのと、「もう一泊30万円ぐらいのホテルしか残っていない」と言われたので諦めました。
しかも日本からカタールへの直行便は満席だったんですよ。だから成田空港からタイを経由して20時間ぐらいかけて行ったんです。エコノミーシートだったので友人は背中にアザができちゃって。そうやって見た試合が「サウジアラビアvsアルゼンチン」です。一番チケットが入手しやすくて。でもリオネル・メッシがいるアルゼンチンを見たいと思って。
前評判はアルゼンチンの方が高かったんですけど、この試合ではサウジアラビアが勝つんですよ。あと数時間いられれば日本戦なのにと思いながら空港に向かって、飛行機の中では爆睡でした。
すると2023年に「Jリーグタイム」のオーディションがあって応募したんです。「Jリーグタイム」は日本で一番長くやっているサッカー番組ですよね。前身は1999年から2001年の「速報・サッカー21」、2002年から2005年までの「速報Jリーグ」ですから、もう26年間続いていいので。私は前任者の中川絵美里さんと仲良くしていただいていたのもあって、ずっと見てたんです。そして採用していただいて、2024年から出演させていただいています。

■試合中はノートにフォーメーションを書いている
実際に番組に出してもらうようになったらそれまでの自分とは変わったと思います。
出演する前まではプライベートの遊びとして見に行っていたので、正直、戦術や監督、ポジション、選手や移籍情報なんかは何となくしか分かっていませんでしたね。点が入って「うわ! この選手うまい!」というぐらいです。
でも、仕事で見るようになってからはいろいろ細かくチェックするようになりました。ここの部分の戦術を変えたからポジションが変わったんだとか、この選手のトラップすごい!とか、そういうのがちょっと分かるようになったんです。この選手はこの戦術で生きるんだ、とか細かい部分まで見られるようになって、より楽しさが増したと思います。
それに試合中、ノートにフォーメーションが書けるようになったんですよ。それまでってなんとなく見ていたから、いざ書こうとすると4-2-3-1なのか4-3-3なのか分からなかったんです。選手が動くと「4バックだと思ってたけれど3バックに見える」とか。
だけど番組に出るようになって2シーズン目になったらちゃんと書けるようになりました。それが自分の成長を感じて最近一番うれしかったことですね。ノートも充実してきたと思います。
試合を見るときは、1チームずつ見開きを使って、フォーメーションや交代、プレーをどう思ったか、試合後に選手に聞きたくなったことを書いています。どちらが勝つか分からないですし、どの選手に聞くかも最後まで分からないので22人見るのですが、そうなると質問だけでどんどんノートが埋まっていきますね。
「このプレーはどんな意図だったんだろう」「あの選手とのこの選手が試合中に会話していたけれど、どんな内容だったんだろう」とか。だから両チームのことだけで4ページ使って、さらにもう2ページ使って、両方のチームのページから試合後に選手にお話を伺うのに適切だと思うものをいくつか選んで書き出しています。
試合が終わったあと、疲れている選手の方がわざわざやってきて話してくださるじゃないですか。本当にありがたいことだから、視聴者のみなさんが聞きたいと思うことを漏れなく聞けるようにしたいんです。話が聞けるのは短いときで3問、多いときで5問ぐらいなんですけど、だいたいは倍以上の質問を用意しています。
でも、やっぱり難しいですね。自分が聞きたいことだけだったらいいんですけど、伝えるという部分では、みなさんが試合を見てて気になったことを聞くのが一番大事なので。「視聴者のみなさんは何を聞きたいのだろう?」と考えることがやはり大変です。もちろん質問はスタッフのみなさんに相談しながら決めるのですが。
■プロチームの練習を見る楽しさがわかってきた
「Jリーグタイム」はJリーグを扱っているので、偏ることなくいろいろなチームを取り上げています。もちろん順位によってどうしても差は出てしまうのですが、それでも下位に沈んでいるからと取り上げないことはありません。偏らないというのは個人的にも心掛けています。
2024年に出演させていただくようになったとき、まずクラブの方に名前を知っていただくところから始めようと思いました。J1でいうと20チーム全部伝えたいということで、去年は20チーム全部のキャンプに行かせていただきました。J1チームの練習場も全部行けましたし、スタジアムも京都の「サンガスタジアム by KYOCERA」以外は全部行くことが出来ました。
その他の企画も自分の「ここに行きたい」「こういう取材がしたい」という意見を番組のみなさんが聞いてくださるので、出来た取材ばかりです。たとえば去年、サガン鳥栖の取材にいったときは、「駅前不動産スタジアム」にいつも出ている、相手チームを歓迎する筆書きのメッセージが気になっていたんです。だからあの紙を掲出している鳥栖高校の書道部にお邪魔させていただいて、私も筆を握らせていただきましたね。
ガンバ大阪のマスコットの「モフレム」に密着しましたし、そういうのもいろいろやらせていただいてるのは、チームを詳しく知るという意味ですごく勉強になりますし、楽しいんです。「Jリーグタイム」は細かい部分まですごく大切にしているので、いろいろな経験が出来てよかったと思います。
プライベートでは、どうしても住んでいる関東中心になってしまうのですが、水曜日に取材がない日などは自分でチケットを買って行っていい。実はいろいろなスタジアムに行ってるんですけど、取材スケジュールが発表されたあとだとチケットが売り切れてしまって行けないスタジアムもあるんですよ。柏レイソルがそうですね。
プライベートのときは公共交通機関で行っています。FC町田ゼルビアにもバスで行きました。無料シャトルバス、ありがたいですね。少し並びますけど、でも混雑もだんだん収まりましたし、クラブが努力しているんだろうというのが分かりました。町田GIONスタジアムは去年まで携帯の電波が入りにくかったのですが、今年は改善されていて、そういう部分もありがたいと思っています。
それから一年間シーズンをとおして見ていると、変化とか違いとか、練習で何を修正しようとしているのかとか、そういうのも少し分かるようになってきました。だから練習場に行くのが楽しみで、練習を見るのがおもしろいですね。
「Jリーグタイム」に出る前にも練習場に行ったことはあったんですよ。北海道旅行したときにコンサドーレ札幌の練習場に行きましたし、川崎フロンターレにも行ったことがありました。でも、そのときは今ほど練習を見る楽しみが分かっていなかったですね。
番組のおかげでサッカーの、Jリーグの楽しみを一つ知ることができたと思っています。でもそういう成長も感じつつも、やっぱり番組で解説者のみなさんやスタッフの方々の話を聞くと、知らないことだらけで、もっと勉強が必要だとか、まだまだというのはすごく感じます。
みなさんの知識量がすごいので、いくら勉強しても追いつくことはないといつも思います。次々に選手は変わりますし、メンバーも変わりますし、もちろん監督が変わったらサッカーもガラリと変わりますし、その歴史もどんどん蓄積されているので、途中から学んでも追いつくことは絶対ないと思うんですよ。でも、その方たちから学べるものを学んで、吸収できるものを吸収して、少しでもその差を埋めていきたいと思っています。

※この続きは「森マガ」へ登録すると読むことができます。続きはコチラ