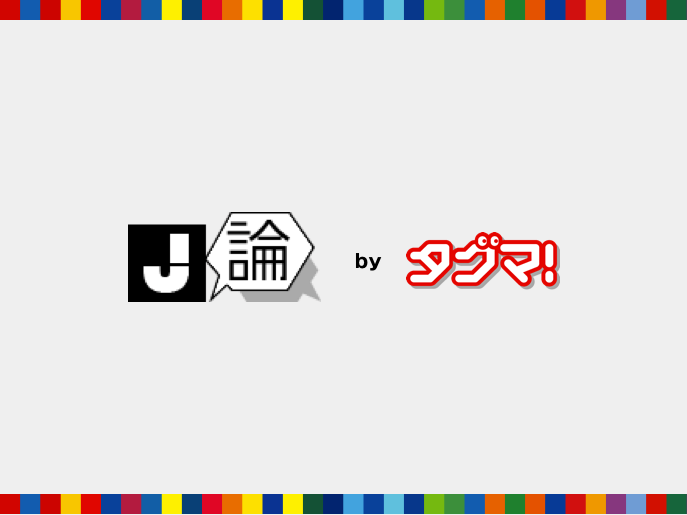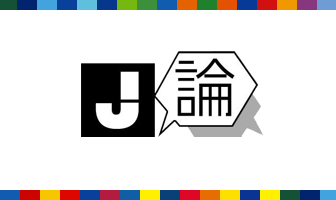鹿島アントラーズは育てて「勝つ」。世代交代で”クラブ力”を示した1年はフィナーレへ
番記者の田中滋が、あらためて今季の成果を振り返りつつ、最終節を展望する。
▼降格すら懸念される陣容に確かな自信
今シーズンが始まる前、大型補強を実施したセレッソ大阪がよもやJ2に降格することを予想した人はいなかっただろう。同じように、鹿島アントラーズがここまで優勝争いに絡むことを予想した人もまた少なかったはずだ。
FW大迫勇也が抜けた布陣は実績に乏しい選手が多く、鹿島らしい戦いを実行するにはあまりにも若すぎた。それが、ガンバ大阪や浦和レッズに比べると可能性は低いながらも、09年ぶりのタイトル奪回を目指せる位置につけていることは、前半戦の不振から立ち直り驚異的なV字回復で首位に立ったガンバの影に隠れているようだが、決して見逃すべきではない事実だ。クラブとしての底力を示しているシーズンと言えるだろう。
しかし、外部からは「降格もあるのでは?」とささやかれていたシーズン前の予想とは裏腹に、クラブ内部では確たる自信を持ってシーズンに臨んでいたという。実際、シーズン前のスポンサー挨拶の場で、鈴木満常務取締役強化部長は「いろいろ言われていますが、心配しないで下さい。そんな順位には絶対になりません」と宣言していたという。昨季1年間でトニーニョ・セレーゾが蒔いた種が着実に芽を出し始めていたことをクラブ側は感じていたようだ。
▼選手を育てるスペシャリストとクラブの空気
そこに、世代交代という難しいミッションを担ったトニーニョ・セレーゾの手腕があったことは確かだ。
トップチームの練習が終わったあと、高卒や大卒の若い選手を集めてプロとして必要な基礎的な技術や知識を繰り返し繰り返し叩き込む情熱は、並大抵の指導者ではないことを物語っていた。戦術家というより、育成のスペシャリストと位置づけられるべき指導者だろう。
しかし、だからといってトニーニョ・セレーゾがどのクラブに行って若い選手を指導しても必ず成功するとは限らない。監督からの上意下達だけでは限界がある。鹿島の凄みは、選手が選手に対してやるべきことを要求するところにある。守備の献身性が足りなければ監督に言われるより先に、まずチームメイトから指摘されるのだ。
できていないことを仲間である選手から指摘されることは抜群の効果を持つ。監督から押しつけられた作戦なら反感が生まれ、結果が出なかったときの言い訳に利用されることさえあっても不思議はないが、選手たち同士で共有するやり方に自分一人が従わないならチームの輪から外されるのみ。
であれば、与えられた選択肢は「やる」か「やらない」かではなく、「やる」の一択しかないのだ。だからこそ、第27節からの4試合、G大阪・柏・神戸・浦和との対戦で勝ち点『2』しか稼ぐことができず、万事休すと思われたところから一致団結しての3連勝でなんとか踏みとどまることができた。
▼ノープレッシャーの強みは、ある
セレッソ大阪戦、先制点を決めたカイオは手の平を地面に向けて上下させ、チームメイトに落ち着けという素振りを見せた。ダメ押し点を上げた柴崎岳もコーナーフラッグまで走ったあと冷静な表情を崩さなかった。試合が終わったあと、勝利を喜ぶのも束の間、ミックスゾーンに現れた選手たちは、優勝の可能性を残して最終節に迎えることに誰一人として目尻を下げなかった。
上位2チームとの勝ち点差は『2』に縮まったが、順位はなにも変わっておらず、最終節のサガン鳥栖に勝って初めて、なにがしかの結果が期待できることを選手たちはよくわかっている。
逆に言えば、そのプレッシャーの少なさが鹿島最大の強みとなっている。勝たなければ優勝できないプレッシャーがかかることはなく、勝つことにだけ集中すれば神様がプレゼントをくれるかもしれないのだ。不安や雑念に縛られることなく勝つためだけに集中できていることは、追いかける者の最大の強みと言えるだろう。
2007年の逆転優勝を飾ったとき、鹿島の最終節の相手は清水エスパルスであり、指揮官は長谷川健太だった。勝つことに集中できている鹿島がどういう試合をするのかを身をもって体験したことがある。過去に獲得した16冠という偉大な歴史は、若い鹿島の姿を実際よりも大きく強く見せるだけでなく、選手を力強く後押ししてくれるはずだ。
田中滋(たなか・しげる)
1975年東京生まれ。上智大文学部哲学科卒。2008年よりJリーグ公認ファンサイト『J’sGOAL』およびサッカー専門新聞『エル・ゴラッソ』の鹿島アントラーズ担当記者を務める。著書に『鹿島の流儀』(出版芸術社)など。WEBマガジン「GELマガ」も発行している。