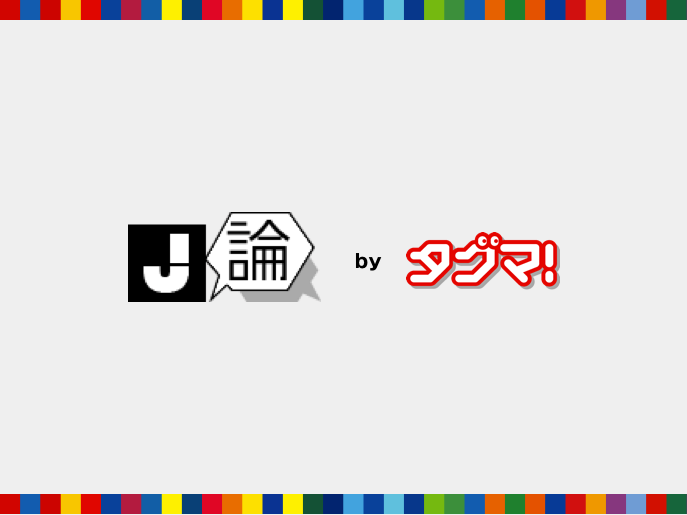ハングリーに、そして強欲に。広島・浅野拓磨に根付いた確固たる逞しさ
リオ五輪を目指すU-22代表の主力の一人でもある新進気鋭のアタッカー・浅野拓磨に焦点を当てる。
▼2014年元日。天皇杯決勝にて
「おまえらは、いったい誰と交代したと思っているんだっ」
2014年1月1日、天皇杯準優勝という悲嘆にくれた選手たちに「お疲れさま」と声をかけていた森保一監督(広島)は、2人の10代選手の前で声のトーンを変えた。厳しく、鋭く、刃のようなトーンで、若者の心にクサビを打ち込んだ。
「0-2と負けている状況で、オレはエース(佐藤寿人)と10番(高萩洋次郎・現FCソウル)に代えて、おまえたちをピッチに送り出した。普通、この状況で交代させられて、彼らが(監督である)オレとの握手を拒否したって仕方がない。だけど、2人はしっかりとおまえらを励まして送り出し、オレと握手してベンチに戻って、チームと一緒に戦った。この意味が、おまえらに分かるか? いいか、そういうチームで、おまえらはプレーしているんだ」
言葉の先には、浅野拓磨と野津田岳人がいた。広島が大きな期待を寄せ、天皇杯決勝ではともに78分から登場した19歳コンビ(当時)。だが、ほとんど自分の色も出せず、チャンスを作ることもなく、相手に脅威も与えることなく、彼らは敗戦のホイッスルを聞いた。
「仕方がない」
何もできなかった2人の若者に対し、周りは責任を問おうとはしなかった。だが一人、森保一だけは違った。
若者を育てるために、2人を投入したわけではない。優勝するために、あえてエースと10番に代えて、10代のアタッカーを起用した。なのに2人は何もできず、結果としてタイトルを失った。その結果に対して「なあなあ」で済ませることはできない。もちろん、2人だけの責任でないことは誰もが分かっている。もちろん、指揮官も承知している。理解した上で、あえて言葉の刃を突き刺した。
浅野拓磨の頬を、熱いものが自然とつたった。
「悔しい……。オレは、何もできひんかった。こんな大舞台に、使ってもらえたのに、チームの役には一つもたたへんかった」
佐藤寿人は「胸を張れ」と2人に声をかけた。
「準優勝は恥ずかしい結果ではない。サポーターにしっかり、顔を上げて挨拶しろ」
浅野拓磨は、こういうエースと交代して決勝のピッチに立ったのである。それなのに……。
「自分に負けた。プレッシャーに負けた」
スポ根マンガのような表現を許してもらえるならば、このときの涙が浅野拓磨という男の(そして野津田岳人にしても)原点だった。男は涙を堪えた数だけ成長するというが、ときには涙を思い切り流して、屈辱と悔恨をその頬に刻み込むことも、男を大きくさせる。
実際、出来過ぎたストーリーが待っていた。涙の決勝から53日後、舞台も同じ国立競技場。再び横浜FMと相まみえたゼロックス・スーパーカップで、野津田岳人と浅野拓磨は見事なゴールを叩き込み、広島優勝の原動力となった。66分、野津田のスルーパスに飛び込み、圧倒的なスピードで横浜FM守備陣を引き裂き、ゴールまでまったくスピードダウンしないで決め切った浅野の姿を見たとき、「2人の時代がやってきた」と心から信じた。
だが、そんなに人生は甘くはない。劇画でもなければ、ドラマでもない。現実は、もっともっと、キツい試練を用意していた。野津田も同様ではあるが、ここでは浅野に焦点を絞って書き進めよう。
▼育まれたハングリー精神
50mを5秒9で走るという単純スピードだけでなく、「キュッ、キュッ」という音が響きわたるようなキレ味。単純な1対1で彼を止めることは容易ではない。ルーキー時代のキャンプでJリーグベストイレブンに輝いた水本裕貴を振り回したトレーニングで、彼の機動性に愕然として以来、間違いなく浅野拓磨は広島を背負って立つと感じていた。彼の生い立ちを知ってさらに、その気持ちは確信となった。
7人兄弟の3番目。大家族は多くの場合、経済的には厳しい。浅野家もまた、そういう環境だった。携帯電話の通話料が払えず、電話が止まってしまうことも決してまれなことではない。家の経済状態を考えると、自分のスパイクを買ってほしいという「わがまま」も言えなかった。お年玉を貯めてやっと一足、先輩から譲ってもらってやっと一足。中学のときまではサッカー部の遠征も、遠征費のことを気にして「別に行かなくても大丈夫やから」と両親には話していた。
それでも、彼は一度も「自分は不幸だ」と感じたことはなかったという。トラックの運転手として日夜走り回り、大家族を支えてくれた父。朝、暗いうちから起きて5つものお弁当を作って兄弟を育んでくれた母。決して経済的な豊かではなかったが、明るくて楽しい家庭を作ってくれた両親への感謝の気持ちは、成長するにつれて膨らんだ。
だからこそ、浅野は高校入学時に四日市中央工(三重)進学を一度はあきらめた。全国レベルの強豪校である四中工に入れば、遠征費がバカにならないと聞いていたからだ。「別に四中工じゃなくても、プロになれる」。浅野自身、そう自分に言い聞かせていた。
そのとき、中学のサッカー部の顧問や担任の先生は、こんな言葉を彼にかけている。
「拓磨、3年間だけ、親御さんに頑張ってくれるよう、頼んでみよう。その後、自分で恩返ししていけばいいんじゃないか」
その言葉を彼は、忘れたことはない。実際、恩師たちは毎晩のように浅野の家に電話して、両親と話し合った。その姿を見つめていた浅野拓磨は、心に想いを刻み込む。
「オレは、プロになりたいんじゃない。プロになるんだ。プロになって親孝行するんだ」
いまやプロスポーツで成功するためには、幼少のころからコーチに付き、クラブに通い、トップクラスの指導を受けないと難しいとも言われている。かつてのプロ野球では浅野のような環境から成功をつかんだ(野村克也や川上哲治が代表的)レジェンドも存在するし、ボクシングや相撲はまさにハングリースポーツだった。「ハングリーでなければ、スポーツ界では成功しない」と言われていたときは確かに存在したのだが、いまはまったく違う時代である。
▼リーグ初ゴールまでのプロセス
その中で、浅野はまさにハングリー。成功したい気持ちは半端なく、トレーニングでは常に100%以上。決してスタミナの豊富なタイプではないため、いつも肩で息をしていた。それでも走り、闘い、泥にまみれた。
ただ、あまりに想いが強過ぎて、気持ちとプレーがうまくかみ合わない。公式戦デビューとなった鹿島戦ではウオーミングアップでバテてしまい、試合に登場したときはヘトヘトになっていた。そうなってはいけないとアップの仕方を変えても、なかなかトップフォームで試合に入っていけない。
ゼロックス杯で公式戦初ゴールを叩き込んだ後は、さすがにアップでバテることはなくなり、強烈なキレ味でビッグチャンスを作れるようにはなったが、ゴール前で焦ってしまい、シュートをGKに当てたりフリーのシュートで枠を外したり。そのたびに天を仰ぎ、首を振った。いわゆる「空回り」。その傾向が、特にシュートの場面で際立っていた。
なぜだ。なぜ得点できないんだ。
悩んだ。苦しんだ。
「ゴールできれば、爆発できるから」
佐藤だけでなく、水本裕貴も森崎和幸も、ほとんどのチームメートが、そんな言葉を浅野に掛けた。だが、そのゴールが記録できない。そのジレンマを打破できたのは、プロ3年目。J1リーグファーストステージ第6節・FC東京戦でのリーグ戦初ゴールまで待たねばならない。
実はその1週間前、浅野は失望のドン底にあった。ファーストステージ第5節・名古屋戦の前半アディショナルタイム、サイドを変えようとしたパスを永井謙佑にカットされ、そのまま川又堅碁につながれて先制点を失ってしまったのだ。
やってしまった……。下を向き、チームメートに謝罪する若者。だが、彼を責める言葉は一つも出なかった。
「おまえならできる。どんどんしかけろ」
これは森保監督の言葉。
「オレは何度もミスをした。30回ミスして、やっとプロと呼べる。お前は1回だけだろ。まだまだだな」
一流の表現で、千葉和彦が励ます。
「次こそ、やってやる。このチームのために」
強い気持ちがさらに加わった。
ゴールはメンタルだけで生まれるものではない。心技体、あらゆる要素が充実しないとネットは揺らせない。実際、浅野には常に強い気持ちがあった。その想いがむしろ空回りし、力みとなってゴールから遠ざけていたことも事実。「もっとラクにシュートを打てれば」。そう考えても、高校時代のような余裕は持てない。強い想いは、自身の体を縛り、重荷や足かせとなっていた。
だが、想いを重ね続けると、それは「空回り」でもなく「重荷」「足かせ」などという次元ではなくなるのだろう。FC東京戦、ドリブルをしかけたときは決してフリーではなかった。最後の局面では日本代表・森重真人が厳しいアタックをしかけてきた。だが浅野は球際の勝負で勝利して森重を置き去りにした上で、駆け引きなどを弄せず思い切って右足を振り切った。
ゴールについて、サッカーについて軽く考えていては、森重を上回る球際の強さは生まれない。そしてそれがJリーグ初得点、しかも当時首位を走っていたFC東京からの逆転勝利を呼び込むゴールにつながったのだ。
▼指揮官による全幅の信頼
考えてみれば、浅野のゴールには試合的にもシーズンを考えても、重要な得点が多い。前述のFC東京戦は3試合連続勝利なしという停滞感を吹き飛ばす逆転弾。19戦無敗を続けていた浦和を止めるきっかけとなった同点ゴールも記憶に新しい。ファーストステージ第13節・新潟戦では2-0のリードを1点差に詰められ、勢いに乗ってきた相手の闘志に水をかけるゴールを決めて事実上試合を決めてしまった。そしてこのときもチームにとっては3試合ぶりの勝利を導く得点でもあった。
カップ戦を見ても、ナビスコカップグループリーグ第2節・湘南戦では後半アディショナルタイムで同点ゴールを叩き込み、第7節・甲府戦では決勝点。チームの苦境を救う得点を次々と決めることができるのは、浅野拓磨という男が持つ「星」というよりも、彼が内面に秘めるほかとは違うレベルの「強烈な意識」の存在ありきと見たほうが素直だろう。
「若くして代表に入って、周りからの注目も熱い。でも、それで天狗になってしまうようなことは、拓磨に限ってはありえない。どういう状況になっても『うまくなりたい』という気持ちを持てるメンタリティー。何も心配していません」
森保監督からの驚くべき信頼が、浅野拓磨の人間性を証明している。これからも彼には、大きな壁が待ち受けているだろう。すんなりと代表定着はないかもしれない。だが、そういう苦境にひざを屈し、続けることをやめてしまうメンタリティーは、彼の中に存在しない。
浅野拓磨は、速い。鋭い。そして泥くさく戦える。それだけの選手ならば、ほかにもタレントがいるだろう。だが、広島の若き宝物の本質的な特徴は、その内面に存在する。そこだけは強い自信と確信を持って、彼を日本代表に送り出したい。
【プロフィール】
浅野 拓磨(あさの・たくま)
1994年11月10日生まれ、20歳。三重県三重郡出身。171cm/70kg。ぺルナSC→八風中→四日市中央工を経て、2013シーズンより広島に加入。J1通算32試合出場4得点、J3通算4試合出場(2015年7月30日現在)。
中野 和也
1962年3月9日生まれ。長崎県出身。居酒屋・リクルート勤務を経て、1994年からフリーライター。1995年から他の仕事の傍らで広島の取材を始め、1999年からは広島の取材に専念。翌年にはサンフレッチェ専門誌『紫熊倶楽部』を創刊。1999年以降、広島公式戦651試合連続帯同取材を続けており、昨年末には『サンフレッチェ情熱史』(ソルメディア)を上梓。今回の連戦もすべて帯同して心身共に疲れ果てたが、なぜか体重は増えていた。