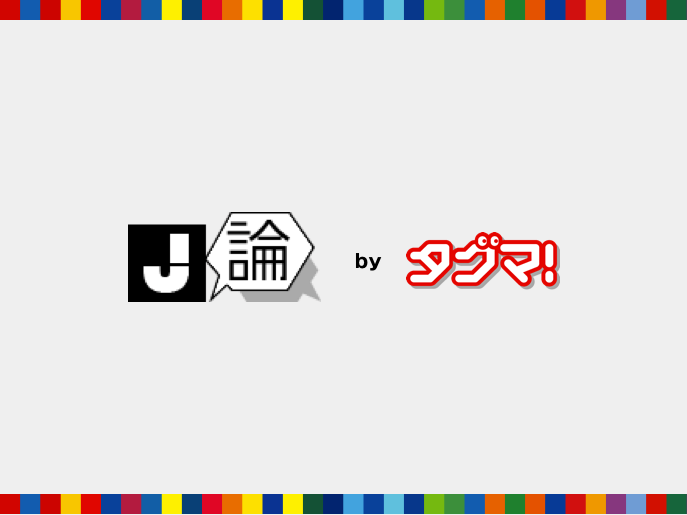青山敏弘はいつも……。ウズベク戦のドライブシュートの軌跡は、あの日のそれと重なって見えた
広島の熱血番記者・中野和也は、青山敏弘のプレーが気になって仕方がなかった。あのコロンビア戦から自分を責め続けていた男のことが......。
▼自分へのナイフを携えて
青山敏弘はいつも、ギラリとしたナイフを自分の中に秘めている。そしてそれは、多くの場合、自分自身を傷つけてきた。
W杯、対コロンビア戦での敗戦を、彼はずっと自分の責任だと背負いこんでいたことも事実である。
「負けたことは、自分の力のなさ。勝っていれば人生も変わったかもしれないけれど、負けたことで何かがストップしてしまった」
広島の3連覇がならなかったことも、自らの責任だと言う。
「連覇した年の終わり頃から、サッカーの内容は良くなかった。キャプテンとしてそこを追求していくべきだったのに、前半戦に結果を残せたことで曖昧になってしまった。自分のコミュニケーション能力が低いから、勝てなくなった。優勝した時は(佐藤)寿人さんがキャプテンとして、うまくチームを回していたということ。新キャプテンの自分には、それができなかったんです」
周りがいくら「それだけじゃない」「違うんじゃないか」と言っても、青山には無駄なことだ。刃はいつも彼の胸にグサリと突き刺さり、時に心をえぐる。突き刺さったナイフを、彼は自分から抜こうとはしない。
▼思い出す風景がある
20歳の青山敏弘もやはり、そうだった。
2006年8月23日、万博競技場でのG大阪戦が脳裏によぎる。52分に山口智、61分に二川孝広にゴールを決められ、広島は窮地に陥った。だが、あきらめていた選手は誰もいない。1点を取れば、流れが変わる。青山も、そう信じていた。
63分、播戸竜二のパスコースを読み,カットしようと走りに走る。ボールは確かに足に当たった。ところが味方につなげようとしたボールは彼の意図と反して、G大阪で最も危険な男=マグノ・アウベスの足下にこぼれた。決定的な3失点目だ。
試合を見ている者からすれば、青山のプレーは確かにミスではあるが、チャレンジシップに満ちたもの。クリアすべきだったというのは結果論であり、つなげばカウンターのチャンス。0-2で負けているのだから、チャレンジして良かった。
だが、本人の考えは違う。
「俺のせいで負けた」
ミックスゾーンでまず出てきた言葉だ。彼が交代した後、続けて2点を取っただけに、その想いはさらに強くなった。ミスからの失点という意味では、2点目もそう。セットプレーから失った1点目も、ミスといえばミスだ。だが、青山の心のナイフは、彼自身をズタズタに切り裂いた。孤独に押し潰されそうになった。
ホテルに戻った後、一人の男が声をかける。
「アオ、行くぞ。ついてこい」
当時のキャプテン=戸田和幸が食事に誘ってくれたのだ。
戸田という男のサッカーに対する突き詰め方は並大抵のものではない。確固たる哲学を持ち、常に理想を追求する。ミスに対する厳しさもまた、規格外だ。
だが、この時の戸田は、青山にそのミスのことを一切、語らなかった。それどころか、生粋のサッカー小僧である彼がサッカーの話題には全く触れない。W杯で日本のベスト16に貢献し、イングランドで戦ってきた男が自ら冗談を連発し、笑いを誘った。
青山は笑った。楽しかった。大先輩の心遣いが、嬉しかった。あっという間に過ぎた大阪の夜は、いつの間にか、彼の心に突き刺さったナイフは刃をおさめ、内側から活力が湧いてきた。
「取り返す。もう出番はないかもしれないが、このままでは絶対に終わらない」
若者の幸運は、当時の指揮官が若者の力でチームを変革しようとしていたこと。G大阪戦から中2日の鹿島戦、ミハイロ・ペトロヴィッチ監督(当時)は何も言わず、黙って青山敏弘の名をスターティングリストに書き込んだ。信頼は言葉ではなく、形として表現された。
この試合で飛び出したのが、35mの距離から放たれた強烈なドライブシュート。その弾道はまさに、3月31日に彼がウズベキスタンのゴールネットに打ち込んだ代表初得点と重なって見えた。
「私が広島に来た時、チームはなかなか勝利できず(2勝4分6敗)、苦境に立っていた。だが、トレーニングを見ているとこのチームに若いタレントがたくさんいることもわかった。青山もその一人だ。彼はよく走れるし知性もあったからね。今日のゴールはセンセーショナルだ。ただ、まだまだ青山は伸びる。これが彼の最後のゴールには、ならないよ」
破顔一笑。
愛弟子・青山のことを語る時、当時のペトロヴィッチ監督は顔中をクシャクシャにしたものだ。そしてJ初得点を叩き込み、勝利の原動力となって20人を越える記者に囲まれた青山を見つけ「アオは1点決めただけなのに、すごいことになっているな」と声をかけ、そして大声で笑った。
「僕は、監督のああいう笑顔が見たかった」
若者ははにかんだ。そして言葉を続けた。
「シュートは会心。打った瞬間に入ったとわかったから、ゴールが入ったその瞬間は見ていなかった。でもね、まだまだこんなものじゃない。満足なんてしていられない」
▼岡山駅のホームで
青山の人生をたどってみれば、心の中のナイフで自分を傷つけ、深い悩みに陥った後、その痛みを癒やすために自らの闘志を奮い立たせる。その連続だったような気がする。
例えば2007年、北京五輪代表候補として注目を集め始めた青山は、何度も泣いた。開幕第2戦、自分のプレーが全くできなかったと大粒の涙をこぼした。開幕10試合で1勝1分8敗と泥沼状態だった横浜FCに敗れた時、広告看板に身体を預け、ペットボトルを見つめながら悔し涙をこらえた。
そして降格が決まった後の契約更改で、またも彼は泣いた。肩をふるわせ、ポトリと目からしずくを落として「まだ、何も考えることができない」と言葉を振り絞るのが精一杯。降格の責任を自らの突きつけていることは明白だった。
この年、青山の心にはたくさんの傷跡が残った。さらに翌年、北京五輪代表落選というショックも重なった。7月14日、大阪から広島に戻る新幹線の中で聞いた、留守番電話に残された「落選」のメッセージ。半分以上、あきらめていたはずなのに、22歳の若者はとっさに岡山駅で電車をおりてしまう。ホームのベンチに腰をおろし虚空を見上げた。1時間すぎても、動く気にはなれなかった。故郷・岡山の空はただひたすらに遠く、どうすればいいのかという問いにも答えを何も用意してくれない。
携帯が鳴った。当時、広島の10番を背負っていた柏木陽介(現浦和)からだった。
「二人ともダメやった。残念会やね」
「今、何してるの?」
青山の問いに、柏木は言う。
「無意味に街を歩いとんねん」
電話を切った後、青山は腰をあげた。誰にも会いたくないと、一号車の一番前の席に座った。
ピッチの上でも外でも、たくさんの言葉をかけてくれた戸田と違い、柏木とはそれほど会話をかわしてきたわけではない。だが、同じ目標を掲げて戦ってきた仲間からの電話に、少し癒やされた。
切り替えなきゃ。切り替えなきゃ。
翌週、反町康治北京代表監督(当時・現松本山雅監督)が北京五輪代表の香川真司を視察に訪れた試合で青山は圧巻のプレーで何度も決定機をつくり、佐藤寿人の同点弾の起点となった。決勝点を叩き込んだ柏木も含め、反町監督の前で実力を存分に見せつけた。それだけではない。前年、「降格の戦犯」であるかのように批判にさらされた森崎和幸と共に中盤を組み、圧倒的とも言えるパフォーマンスで残り7試合を残してJ1復帰を決定。後にリーグ連覇を果たす広島サッカーの礎を築いたのだ。
▼覚悟という武器と共に
昨年、W杯日本代表選出という僥倖の後、青山は深い底に落ちた。コロンビア戦で腰を傷め、大宮戦で再発。開始早々にピッチを去ったその試合では3点差を追いつかれ、またも自分に対して刃を向けた。復帰しても調子はあがらず、「自分のところでスイッチが入らない」と責め続けた。「2014年は負けたことが収穫」とまで言い切った。
J初ゴールを彷彿とさせた強烈なミドルシュート。精密なダイレクトパスによるチャンスメイク。日本中に青山の力を再認識させたウズベキスタン戦だけでなく、昨年はほとんど見られなかった強烈な縦パスによる佐藤寿人のゴール演出(開幕戦)を含め、コンディションはいい。昨年、自らに向け続けた刃による傷も、少しずつ癒えつつある。
おそらく、青山敏弘は自身の中にあるナイフとの戦いを、これからもずっと続けていくことになるだろう。ここまでは、様々に人の助けを借りながら、その戦いに勝利してきた。では、次も勝てるか?それはわからない。人生とは未知数の集積だ。
だからこそ、彼は自分に言い聞かせ続ける。
「自分が沈んだのは、自分の努力が足りなかっただけ。絶対に巻き返す。俺はこんなものじゃない。第一、俺には運がある。プロサッカー選手になれたのも、W杯に行けたのも、運がないとできないことなんだから」
そして男は、自分との無限の戦いに向けて、今日も明日も、走り続ける。覚悟という武器を磨き続けて。
中野和也(なかの・かずや)
1962年3月9日生まれ。長崎県出身。居酒屋・リクルート勤務を経て、1994年からフリーライター。1995年から他の仕事の傍らで広島の取材を始め、1999年からは広島の取材に専念。翌年にはサンフレッチェ専門誌『紫熊倶楽部』を創刊。1999年以降、広島公式戦651試合連続帯同取材を続けており、昨年末には『サンフレッチェ情熱史』(ソルメディア)を上梓。今回の連戦もすべて帯同して心身共に疲れ果てたが、なぜか体重は増えていた。