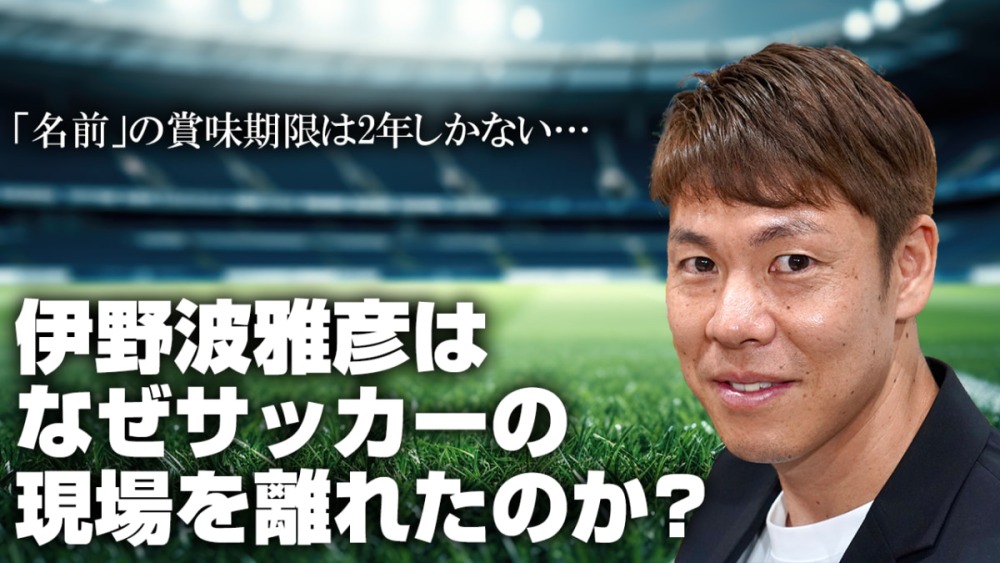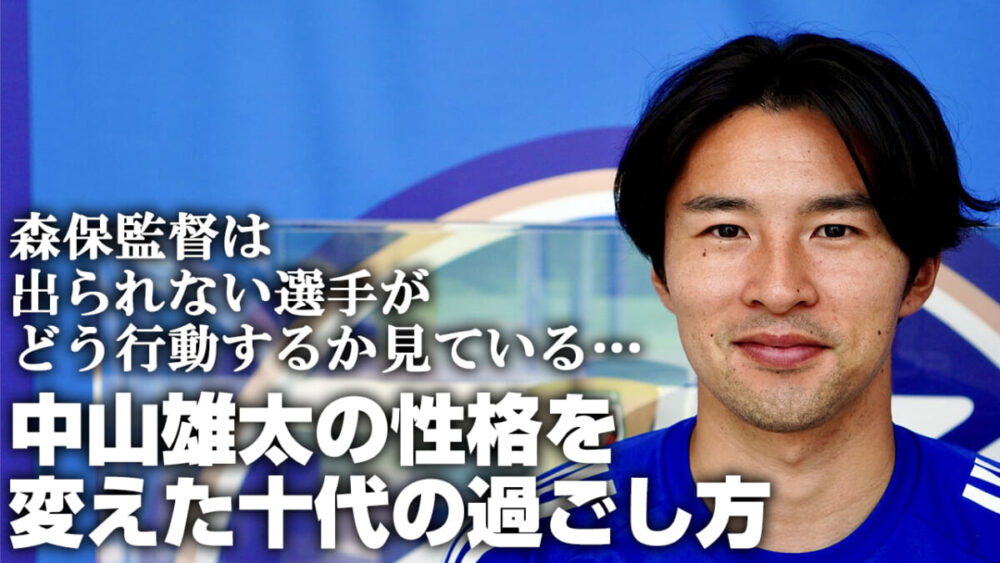
森保監督は出られない選手がどう行動するか見ている…中山雄太の性格を変えた十代の過ごし方【サッカー、ときどきごはん】
ケガから復帰した最初の練習後
報道陣から「お帰りなさい」と言われると
「そう言っていただけてうれしい」と笑みを浮かべた
その明るさに聞いたほうが胸をなで下ろしたくらいの笑顔だったメンバー発表後のケガでワールドカップのメンバーから外れることになった
しかしそれよりも辛かった時期があるという
昔は今と性格が真反対だったという
中山雄太にターニングポイントとオススメのレストランを聞いた
■引っ込み思案の少年はなぜ変わったのか
僕は昔からこういう性格だったかというと、むしろ真反対だったと思うんですよ。人に会うのはあんまり好きじゃなかったし。サッカーは好きなんですけど、選抜チームに行くと知らない人たちとプレーするのがあんまり好きじゃなくて。
話に入っていける性格でもなかったですし、引っ込み思案というか人見知りというか。プレーには自信があったんで「サッカーできてればいいか」ぐらいな感じですよ。今とはホント真逆に近い性格だったと思います。
それが変わったのは経緯があるんです。
僕の経歴だけを見た人からは、柏レイソルのアカデミーに入って、プロになって、プロでも2年目でリーグ戦に26試合出て、海外に行って、日本代表にも入ってと、すごく順調に来たように思われるんです。
でも、ところどころに、経歴には載らない、分岐点になるような挫折というか悔しい思いをする時期があったんですよね。僕の中では知られているような経歴よりも、どちらかというとその苦しい時期のほうが多くて、その経験が徐々に自分の性格を変えていったと思います。
最初の挫折は小学生のとき、県選抜のもう1ランク上の関東選抜に落ちたことでした。ただそのときは今みたいな性格ではなかったので、どちらかというと選抜にあんまり行きたくないと思ってたんです。県選抜のときは「選ばれたならしょうがないか」と思って行ってました。だから関東選抜に選ばれなかったときは「自分はこんなもんか。楽しくサッカーできればいいや」ぐらいしか思ってなかったんですけどね。
中学1年のとき、レイソルの下部組織との練習試合があったんです。そこで活躍すればいろんなチャンスがあると思ってました。けれど、そのとき風邪をひいて休んでしまったんですよ。そこもショックでしたね。
だから2年のときは「こんなチャンスはない」とモチベーションがいつも以上に高かったんです。そこで結果を出したんで3年生からレイソルに入ることになりました。
だけどレイソルに入ってからは人工芝に慣れなかったり、ナショナルトレセンに入って忙しくなったり、それまでと違う1年の過ごし方をしたりといろんな要素が重って大きなケガをしたんですよ。
足首のかなり珍しい症例で、何が原因かなかなか分からなかったんです。よくなっている感覚があって練習に行くと、すぐまたその日に痛くなって。中学から高校までずっとケガを引きずって4、5回再発したんで、もう治らないんじゃないかと不安で仕方なかったです。そのときはメンタル的にきつかったですね。
それまでの人生で一番大きなケガで、「サッカーを辞めようかな」と思ったりもしました。いつも痛みに悩まされていたから「もうサッカーはできない」って。高校進学のタイミングでもあったんで、スパっとサッカーを辞めて高校行って、高校の部活でプロも目指さない、楽しくやれるサッカーで終わろうかとも考えてたんです。
そのころは高校生なんで、サッカーをすることに生活がかかってるわけじゃなかったから逃げ出すのは簡単だったと思います。でも逃げないくらいサッカーが好きでした。あとは家族とか友達も含め、レイソルのアカデミーのいろんなスタッフみなさん含めてのサポートがあったんですよ。あれがないと無理だったと思いますね。周りの力っていうのは絶対必要だったなと思います。
ケガに向き合ってるうちにメンタルは強くなったと思います。「何事も継続すること」が大事だと思っていたので、自分のメンタルをそっちに構築しました。治るか治らないかわからないけど、それでも練習を継続していれば絶対自分の力になると信じることにしたんです。
治ったと思ってやってみたらケガする。もう一回リハビリと練習を継続してみる。そしてまたケガするという感じだったんですけど、最後のケガの時に原因が判明して、手術しました。
それで完全に治ったときに、何回も繰り返したケガの期間がすべて繋がったんですよね。「終わりよければすべてよし」じゃないですけど、どこかでサッカーをひたむきにやってない期間があったとしたら、それだけで損するんだと最後に分かったんです。
なかなか完治には至らない怪我でしたが、手術をしてパッと治りました。でもそれが10代の中で一番大きな出来事で、自分の性格を構築していく一つの大きな事象でした。
いい未来が来ないかもしれないけど、信じてやり続けることは無駄じゃないんだと心から思えるようになりました。ケガでメンタル的に壊れそうになったり、ちょっと壊れたりしたけど、逆にケガが向上心を持つきっかけにもなったんです。
中高時代にケガに対する気持ちだったり、考え方はだいぶ変わったと思いますし、必然的にメンタルが強くなりましたね。サッカーじゃなくても日常生活の中で、嫌だとか、難しい、逃げ出したいと思うことに対する取り組み方も変わりました。
苦しいときでもやり続けることで、未来に向けて貯蓄ができるという感覚が得られてたんです。うまくいかないとか、逃げ出したいときに、本気で乗り越えたら強くなれるし、「乗り越えるチャンスは強くなるチャンス」と思えるようになりました。問題を乗り越えようとしたり、乗り越えた結果で構築されたのが今の自分だと思います。今はもう全然昔のような性格ではないです。
昔は人の前で発言するのもそんな好きじゃなかったですし。今ではいい意味でも悪い意味でも、自分の中で話したいことを話すようにしてます。喋りたくないときもあるし、そのときは「今ちょっとすみません」「今はそういう質問あんまり受け付けてないです」と言って断りもします。
分かりやすいと思いますね、僕。表裏ないから。そこはハッキリしようと思ってるんで。海外で白黒はっきりつけるっていう性格になっちゃって、日本人の良さは失ってますけどね(笑)。

■難しい道を行くほうが成長できる
でもすべて順調というわけじゃなくて、最後のU-18プレミアリーグで東西対抗の日本一を決める試合で最後に負けたり、プロ1年目の2015年はほとんど試合に出られなかったりしました。
2年目の2016年も試合に出られないかもしれないと思ってたんです。でもチャンスが来て出られるようになりました。その年に就任した下平隆宏監督が若手を積極的に起用してくれて、中谷進之介さんとコンビでセンターバックとして使ってもらったんです。
そこは運がありました。でも使ってもらえるだけの実力も示せたと自負もしてます。運とタイミングが来るまでずっと準備するだけの継続力を持っていたのが実を結んだと思います。
それで、ある程度試合に出られるようになったら、自分の成長幅をもっと広げたい、もっとうまくなりたい、もっと強くなりたいと思い始めて、それで2019年1月、オランダのズヴォレに行くことにしたんです。
今だから言えますけど、そのタイミングで国内移籍の話もありました。自分たちより順位が上のクラブからのオファーでしたね。けれど自分の目標とか、何を成し遂げたいかを考えて逆算して海外を選びました。
そのときもらっていたオファーの中では、タイミングも含めて間違いなく一番難しい道を選んだと思います。当時でもその自覚はありましたし、周りからも言われました。
でもそれが自分の中では一番自信を持って選んだ道だったんです。それまでの期間、難しいことや、逃げ出したくなるようなことがいっぱいありましたが、そういう「難しい期間」イコール「自分が成長してきた時間」だったという自覚があったんですよ。だからこそ難しいほうが成長できる道なんじゃないかと思って選んじゃうんですよね。
自分でもたまにもっと別の道を選んだほうがよかったんじゃないかと思うんです。けれど、なんかワクワクするのはそっちじゃないんですよね。難しそうと思うほうを選びたくなっちゃうんですよ。で、選んだら間違いなく難しいんで、もがくし、ストレスも溜まるんですけど、結果、それを乗り越えていく楽しさとか、自分が乗り越えていくときに成長を実感できるから、そっちを選んじゃうんで。
ズヴォレの最初のシーズンは出場が4試合でした。帰ろうとは思わなかったですけど、思ってもおかしくない状況だったと思います。出られなくて本当にムカついてたし、出たらやれると思いつつ日々を過ごしてました。
その状況にもがきながら、いつか出られるように、そしていつか試合出場の機会が来たら、そのときにいいパフォーマンスが出せないと本末転倒だと思い、いつでもチャンスが来ていいように準備し続けてました。
2021年にはイングランド2部のハダースフィールドに移籍しました。自分のニーズに合ってたんですよ。そのころの僕はある程度オランダでもやれるようになってましたけど、個人としての打開力だったり、ピッチ内での個人での解決力はまだまだで磨かないといけないと思ったんです。イングランドに対人プレーだったり、デュエルという個人能力が問われる部分を求めに行った感じですね。
2022年カタールワールドカップの1年前だったから、人からは「新しい環境で出られなくなるリスクを考えると難しいタイミングでの移籍じゃないか」と言われたこともあるんですけど、全然気にしてませんでした。そこがあんまりよくないのかもしれないですけど(笑)。
このときも、「オランダにいたほうが安定していたり、オランダでのプレーのほうがよく見えるものが多いから、そっちを選んだほうがいいんじゃないか」と周りは思ってるのが分かってるんです。けれど、自分が選びたい道はそっちじゃなかったんですよね。
自分が欲してるものとじゃないと続かないですからね。刺激がないと無理なんで。そして難しいという刺激には、成長できるチャンスがあるんで、僕はそっちを選びがちだと思います。2022年カタールワールドカップの1年前でも移籍を選んだのは、僕の中のプロセスで一番必要な部分を得られる場所を選んだ結果です。
そしてそれはワールドカップで活躍したり力を発揮するために必要だと思ってて、逆算したらハダースフィールドが一番よかったんです。2024年、帰国することにしたとき古巣のレイソルじゃなくてFC町田ゼルビアを選んだのもそうですね。
■森保監督は選手の行動を見ている
2022年カタールワールドカップのアジア予選で日本代表は前半長友佑都選手が出て、後半僕が交代で出場するというパターンになってました。表情には出してないんですけど、「プレーさせてほしい」というオーラは出ちゃってたと思います。
「試合に出たい」というのをプレーに出したり行動として出すのは選手は選手としてやってはいけない態度だと思います。だから自分が出られないことへのストレスは感じつつも、「よくない選手」にならないように何をすべきか考えてました。
そして結局自分の実力不足だという結論に落ち着いたんです。「他責」志向じゃなくて「自責」になった。自分に矢印向けるというのは、オランダの初年度でも意識していました。
自分の実力が足りないからこそ使ってもらえない。自分がリオネル・メッシやクリスティアーノ・ロナウド、エムバペやセルヒオ・ラモスだったら出られるんですよ。結局スーパーな選手だったらどんな監督にも使われるんです。
だから出られない悔しさを自分の成長にシフトしました。それは僕の中ではある種の特技だと思ってます。それに僕はマイペースなんで(笑)。
ただチームの輪に入りつつも、仲良くやる必要もないと思ってます。それでも変に敵対するようなこともしないですし、自分が出られないフラストレーションとかストレスを溜め込んで、自分のパワーに変換して、それを放つという枠で収まればいいと思ってます。
出たいというオーラを出すのは、一つ間違えれば和を乱すことがありますけど、出られない選手がテンション感とか、「出たい」という雰囲気を放つのがいいこともあるんですよ。
出てる選手へのプレッシャーというか、「オレたちもやらなきゃ」とか「あいつも出たいよな。自分が出るからにはちゃんとやろう」とか、相乗効果が生まれてくるんです。和を乱さないようにしつつ「出たい」という雰囲気を出すような、うまい具合のコントロールが選手に求められてると思います。
森保一監督は選手の感情が分かってると思いますね。直接話してくれるタイプの監督だし、自分のフラストレーションが溜まってることや、試合に出たいという雰囲気が出てるのも感じてたと思うんです。そして森保監督は出られない選手が次にどう行動するかを見てる人だと思ってます。
※この続きは「森マガ」へ登録すると読むことができます。続きはコチラ