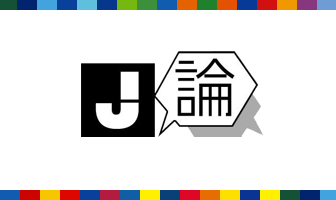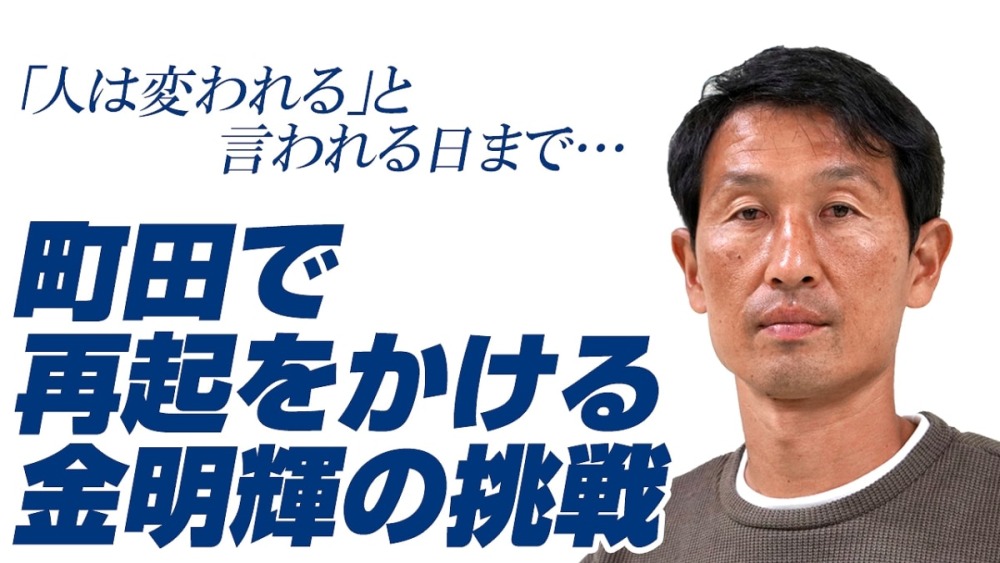来日45年の英国人記者はJリーグをどう評価する?…マイケル・プラストウが見続けた日本サッカーの進化【サッカー、ときどきごはん】
Jリーグができるはるか前
まだ日本サッカーリーグだったころから
日本サッカーを取材しているイギリス人がいる
イギリスの雑誌に35年間、寄稿し続けているという冷静な目で日本サッカー界の変化を見つめてきた
今も広い視野で日本サッカーを眺めている
ときに辛口に聞こえる意見も言えるだけの知見を持つ
マイケル・プラストウ氏に日本サッカーの分析とオススメのレストランを聞いた
■日本サッカーの記事を担当して35年
日本に初めて来たのは大学を卒業する1980年ですね。大学を出て、ちょっと真面目な仕事をやる前に世界を見たいと思って来ました。
大学でインドや中国関連を勉強したんです。それで大学の2年生と3年生の間の夏休み、インドに行きました。バックパックを担いで、外で眠るような旅だったんですけど、もっとアジアを見たいと思いました。
それでアジアに仕事ないかと調べて。日本はちょうどそのころ、高等学校などで英語を教える外国人を探してたんです。今はALT(アシスタント・ランゲージ・ティーチャー)と呼ばれる制度になりましたが、当時はまだ実験の段階で、アメリカ人40人、イギリス人40人雇おうとしてたんですね。
私は教員になるための資格は持ってなかったんです。英語を教える資格がないだけではなく、外国語も16歳までしかやってなかった。けれど、そういう資格はなくていいということだったので申請して、採用されました。
それで群馬県に行って、3年間。最初は一年契約で、更新は二年。もとより、更新は一回までだったが、2年目が終わろうとするところ、教育委員会にもう1年でもいいよと言われた。その仕事が楽しかったし、結果的に太田高校、高崎高校、桐生高校、1年ずつ教えました。
それから群馬大学の仕事の話も始めたんです。学部生に英語で科学の授業をしました。私の最終学位はたまたま自然科学だったので、科学の歴史と哲学の資格を持っていたんです。だから1984年から学部生のための授業をしたんです。それから放送局の仕事もやるようになりました。海外放送向けの原稿中心ですね。
大学の仕事は1992年までやってました。なぜ1992年までかというと、1993年にJリーグが始まったから。
あの当時の大学は週休二日じゃなかったですね。当時すでに取材していた日本サッカーリーグ(JSL)は日曜開催だったけど、Jリーグは土曜日もあった。大学がもうすぐ週休二日になるというのは分かってたけど、でもそのころは違ってたし、群馬大学では土曜日に授業を持ってたからJリーグに行けない。それで群馬大学は辞任しました。そこから別の大学で1996年まで教えて、放送関係の仕事はいつもメーンだったが、他にもヤンマーディーゼルのコピーライテイングなどもいろいろやってました。
最初のサッカーの取材は、1984年8月25日に国立競技場で開催された釜本邦茂さんの引退試合ですね。その試合のことをヤンマーディーゼルの社内誌に書いたんです。
それからJリーグを作ろうという話とワールドカップ候補地の話が出てきて、イギリスのサッカー雑誌の「ワールドサッカー」が日本に興味を持ったんです。
私はメディアの仕事をやってたし、すごく楽な仕事だろうと思って受けたんです。読者は日本にはそんなに関心がないだろうと思ってました。でもイギリスでは日本への関心がJリーグ以前と比べるとかなり高くなってたと思います一番関心高かったのが、1990年代の前半から後半に入ろうとしているとき。「ワールドサッカー」には毎月2ページぐらい日本の記事が載りました。
あのときはInstagramなどもなかった。だから英語圏では国際サッカーについて知りたい人にとって「ワールドサッカー」は一番先に読むものでした。その意味で価値があったと思います。
当時は、「ワールド・サッカー」はやや短い記事で、出来るだけ多くの国の情報を毎月紹介する編集方針だった。今はもっと長い特集が組まれてます。今なら、日本は年に4回、多い年は6回から7回は特集されます。
ワールドカップの年は「ワールドサッカー」で記事を書く機会が増えます。ワールドカップ特別号が出るので、サッカーファンはかなり読んでいると思います。毎回、その特別号に出るチームの全監督のインタビューが掲載されます。
あとは90年代、公式Jリーグニュースの印刷物の英語版を書いていました。「ワールド・カップ招致員会」の英語版ものもありました。その後、Jリーグのサイトが出来たとき、最初はジェレミー・ウォーカーさんがウェブサイトをやってたんですけど、彼が日本を離れたのでその仕事も長年引き継ぎました。今は「ワールドサッカー」がメインですね。日本の記事は35年間、担当し続けています。
■80年代から日本サッカーは強かった
日本に来て45年経ちますが、来日した当時はサッカーがそこまで盛んじゃなかったですね。テレビで放送されるのは天皇杯の準決勝、決勝ぐらい。1980年代は「三菱ダイヤモンドサッカー」が放送されてましたね。今週は前半だけ、来週は後半だけという放送でしたけど、当時多くの試合は結果が分からなかったからそれでもよかった。
日本で最初に観に行った試合はトヨタカップです。1981年2月11日のイングランドのノッティンガム・フォレストvsウルグアイのナシオナル・モンテビデオ。0-1でナシオナルですね。
ブライアン・クラフ監督(故人)が国立競技場の枯れた芝を見て「日本の芝は全部茶色い」と言った試合です。それからトヨタカップは大体毎年見てたと思います。
1984年の釜本さんの引退試合だけは半分仕事のような感じで行きました。ヤンマーディーゼルの仕事をやってましたから。ペレもいてオベラーツもいて。そのときの記事も持ってます。
日本代表を初めて観たのは1985年10月26日の1986年メキシコワールドカップ・アジア最終予選決勝戦第一戦の日本vs韓国ですね。1-2で、木村和司さんのFKの有名な得点があったけど結局負けた試合です。
でも、そのときもよく考えたら日本は東アジア2位なんですよね。あのときワールドカップのアジア枠は2カ国でしたけど、1998年の3.5枠、2006年以降の4.5枠あったら出られた。韓国のほうが上だったにしても。
よくみんな日本のサッカーが強くなった、日本はワールドカップに毎回行くようになったからと言うけど、本当はその当時も枠があったら出られた。1990年は難しかったかもしれないけど、1994年は惜しかった。ハンス・オフト監督のときですね。
でも1980年代にはアジアクラブ選手権(現AFCチャンピオンズリーグエリート)で1986年に古河電工が、1987年には読売クラブが優勝してたし、かなりレベルは上がっていたと思いますね。
日本代表は1989年に、1990年イタリアワールドカップ・アジア1次予選の朝鮮民主主義人民共和国(北朝鮮)戦やインドネシア戦も見に行きました。北朝鮮には2-1で勝ち、インドネシアには5-0で勝ちましたね。
1990年代に入ってもセレッソ大阪についてヤンマーの社内報に数回書きました。そのころはもうすでに軽い感じでサッカー取材してました。本格的な取材は1991年のキリンカップ。対戦相手はタイ代表とブラジルのバスコ・ダ・ガマ、それからイングランドのトッテナム・ホットスパー。あのころ日本代表の相手として他の国の代表チームを呼ぶのは難しかったんでしょうね。
もちろんクラブチームを呼ぶのも難しい面があるけど、シーズンオフだったら呼べますからね。あの大会で日本代表は初優勝したと思います。最後、国立競技場でトッテナムに4-0で勝って。
トッテナムは若い選手が多かったけど、ガリー・リネカーもいました。その当時の日本代表はどんどん強くなっていったんです。カズ(三浦知良)がいて北澤豪は非常に存在感がありました。あとはラモス瑠偉、井原正巳。森保一はまだいなかったですね。
ほぼ同じころから日本サッカーリーグを取材するようになりました。その当時が今ほど強かったかというと、そうではないと思いますけど、それでも世界全体も今ほど強くなかった。そしてJリーグになってまるで違う世界になっています。それはいいことです。
■今でも気になる地元クローリー・タウンFC
私が生まれたのはロンドンの近くです。最初に観に行ったチームは地元のクローリー・タウンというチームですね。最初に見ていたのは1960年代の終わりで、そのときはセミプロでサザンリーグ、つまり5部リーグでした。
今はイングリッシュフットボールリーグ1部、つまり国の3部リーグです。去年はリーグ2部、つまり国の4部で7位になってプレーオフで昇格しました。今は1部にあまり残りそうもないですけどね。今もクローリータウンの試合があると、時差があるから朝一番、どうなったか確かめてます。
イギリスに帰るとき、多くの場合はクローリー・タウンの試合を観に行きます。それは少年のときからファンだったからですね。ホームは全部行ってたし、スカーフも帽子も全部持ってたし。アウェイにもときどき行っていました。チケットも安かったですし、アウェイ戦のときもバスが出ていて、そのバスの子供料金も安かったですね。
地理的に近いところ、ブライトンとかクリスタルパレス、ミルウォール、ウインブルドンの試合もある程度見に行ってたんです。その中で一番見たのはブライトンとクリスタルパレスですね。住んでいたのが、両クラブのちょうど中間のところぐらいですから。
私が10代だった1970年代はフーリガンがもっとも問題になっていた時代ですね。ミルウォールはその中でも怖いチームの一つでした。試合の日に行くと大勢の人がいたんですけど、フーリガンはフーリガン同士で喧嘩するから、13歳の少年には誰も興味がなかった。その点は非常に安心できました。試合日じゃなかったらあの土地は感じとしてちょっとヤバいところだったですね。
ブライトンとクリスタルパレスは逆にそういう問題がそれほどなかった。両親は心配したかもしれないけど。でもあのころ子供が友達と一緒か一人で行くことは平気だったんです。今は両親と一緒じゃないとなかなかできないと思う。
そのころは立ち見のほうが多かったし。立ち見では見えるものは結構限られてるけど、それが当然だったという感じで全然気にしなかったですね。見るところ見て、見えないところは雰囲気を感じてました。スタジアムに行く習慣がちゃんとついてました。
日本でサッカー観戦する少年たちと、イギリスでその当時、また今、観戦している少年たちは違う経験かもしれないですね。でも、クローリー・タウンみたいなところだったら、特にJ3だったら共通点があると思います。それは本当に地元の雰囲気で、自分のチーム、周りの人はみんな自分と同じ言葉喋ってるような感じで。
クローリー・タウンは、その当時よくて観客600人ぐらいですか。悪いときは300人とか。クローリー・タウンのFacebookのサイトがあって、その中ではクローリー・タウンの最低観客動員数のリストが出ました。16人だったか。その試合、僕は行ってました。
それは昔のヤマザキナビスコカップっぽい、23歳以下の選手が中心の試合で、完全なトップチームと言えない試合で。本当に寒い夜だった。滅多にないぐらいの寒さ。その試合、0-10で負けました。非常に良く覚えてますね。0-10で負けることは、クローリー・タウンでもなかなかないです(笑)。
■Jリーグは出来たタイミングが非常にラッキーだった
私も予測しなかったけど、Jリーグは急に人気になりました。外国から今は考えられないくらい有名な選手が来ました。1994年アメリカワールドカップの優勝チームのブラジル人選手だけじゃなく、何人も。
Jリーグは出来たタイミングが非常にラッキーだった。あと1、2年経っていたらバブル崩壊の影響でできなかったかもしれない。さらにその数年後だったら、世界的に有名な選手を呼ぶにはお金がかかりすぎたでしょう。サッカーの世界そのものが本当に変わっていった時代で、Jリーグはその先端だったと思います。
イギリスから見ても、Jリーグは面白い話だった。たくさん小さいところが違っていた。今はみんな当然のことと思うけど、たとえばチームキャラクターがピッチに出るとか、そういうことはあの時代のイギリスではなかったですね。今はどのイギリスチームでも、クローリー・タウンも含めてキャラクターがいます。
そしてヨーロッパはフーリガンの時代から変わりました。イングランドは特に「ヒルズボロの悲劇※1」や「ヘイゼルの悲劇※2」があって、スタジアムを全部座席にしようとする世の動きとか、サッカーを家族的なものにしようとしていました。女性や子供が気軽に行けるように。それまでも子供は気軽に行ってたんですけど、でも家族として行けるような場所に変わっていたんですね。
ちょうど同じころ衛星中継が始まってました。それでサッカー界に資金がどんどん入ってくるようになって、みんなが想像しなかったビジネスの規模になってきたと思う。
Jリーグはそんな恩恵をすべて受けることできた。世界的に自国リーグ以外のサッカーへの関心が急激に高まった。新しいやり方を探していた。Jリーグは新しいやり方の1つでした。かなり有名な選手が集まってたから。すべての国、サッカー先進国というなら、アルゼンチン、ブラジル、ドイツ、イングランド、イングランドは一人だけですけど、などから一流選手が来てたんですね。
ちょっと年齢の高い選手もいた。でもすべてがそうというわけじゃなかった。セザール・サンパイオなんかは一番いいときに来てた。ドゥンガもそう。引退前で金を稼ぐためと言うより、選手たちも監督たちも、何か新しいものに関わりたい気持ちが強かったと思います。
Jリーグはラッキーという部分もあったんですけど、日本のサッカーそのものは1980年代の後半にはもう次の段階に行くような力が確実にあったと思う。古河電工や読売クラブがアジアで優勝したりとか、日本代表がもうワールドカップに出られるか出られないかギリギリの線に入ってるとか。でも、プロになる受け皿はなかったんですね。
全国リーグである日本サッカーリーグは1965年からあったし、プロリーグが成功する条件はすべて揃ってたんですね。私は最初、全部揃ってることに気付いてなかった。あんまりたくさん見てなかったから。大きなスポンサーがバックにつけば、まあまあ上手くいくだろうと思ったけど、Jリーグが実際にあんなに早く世界的な存在になるとは予想していなかったんですね。
その当時はJリーグ、どこまで成長するかと疑問もありました。10チームだけだったし、10チームだけでは強くなるはずはないんです。昇格、降格がないような、競争があんまりないような、そういうものはサーカスに近いようなものになる恐れがあるんですね。
上手い人が集まって、毎週アイスダンスをやる。オリンピックのフィギュアスケートじゃなくて、アイスダンス。エンターテインメントとしては面白いかもしれない。でも、本格的なサッカーリーグになれるか、そこまではわからなかった。それが今60チームですね。昇格降格もありますし。
始まって30年後に60チームになった。まだ解散したチームも1つだけ。横浜フリューゲルスは解散と言うよりは吸収。これからは出るでしょう。でも、基本的にもうほとんどの県にチームがあるし。クラブが増えてる県もある。
組織的には受け皿が豊富です。あとは、明らかに最初の頃より強いですね。日本のサッカーを取材し始めた1980年代、1990年代は非常に楽でした。選手は最初のポジションでずっとプレーしてた。今はかなり流動的で創造力も豊かです。最初のころ外国人監督は「言ったことはやるけど、言われてないことはやらない」と文句言ってました。
今、そんなことないと思う。三笘薫みたいな選手もいる。どんな状況でもすぐいい判断できるような選手が出てきましたね。中田英寿さんはスペースがあるようなポジションで、広く見えたようなところでプレーしてました。三笘はほんとにスペースがないところでも、すべてわかってやってますね。
■Jリーグはいい選手を輩出するリーグになったけど…
Jリーグはベルギー、オランダ、ポルトガルリーグみたいな、あるいはスイス、オーストリアみたいな存在になりました。確実にいい選手が出る。いい選手が出てくるリーグになってます。
日本のいいところは、まず選手から見ると、やりたいならやれるところがあります。外国に行きたいなら、外国に行く道がもうできてます。外国でもJリーグでやってる技術は通用するとわかってる。外国でも自信持ってプレーできる。
※この続きは「森マガ」へ登録すると読むことができます。続きはコチラ