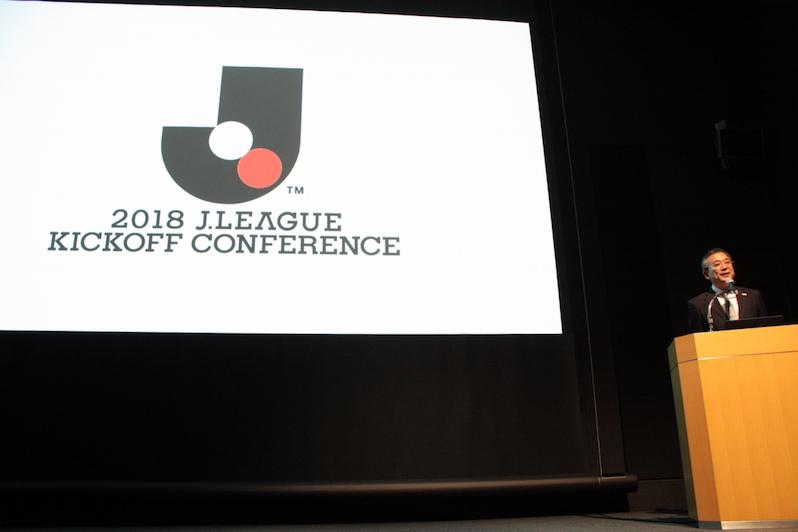経営再建からJ1昇格へ。プレーオフ制度は、”一獲千金”の夢売るシステム
大分トリニータの番記者・柚野真也氏がこのテーマを斬る。
▼J1昇格はご褒美
2012年、初めてJ1昇格プレーオフ制度が導入されたシーズンに、大分トリニータは”下克上V”で昇格を果たした。あの年の大分は”神っていた”。
クラブは経営再建中でJ1昇格を果たすには、成績面以外にも高いハードルが残されていた。2010年にJリーグの公式試合安定開催基金から借り入れた6億円の未返済分3億円を、リーグ最終戦1カ月前までに返済しなければ、自動昇格はもちろん、プレーオフ出場の道も断たれる状況だった。
クラブを運営する大分フットボールクラブの青野浩志前社長は、「われわれフロントは財政面で、監督、選手は成績で高いハードルをクリアしていかなければならない。双方でプレッシャーをかけながら苦難を乗り越えたい」と語り、ノルマ達成に向け走り続けた。人件費や運営経費の削減で2期連続となる1億円以上の黒字を出し、実質債務超過額を9億1800万円まで圧縮した。しかし、Jリーグへの未返済分3億円を期限内に自力返済できる体力がないことは明らかであり、一般の個人やグループから寄付金を募ることにした。
この非常事態に県全体が立ち上がり、県民からの支援金は開始から3カ月弱で1億円を超えた。支援のうねりは大きくなり、自治体、地元経済界をも巻き込み、最終的には約3億3,000万円の支援金が集り、Jリーグへの借入金を返済した。そして、チームは三位一体の支援に後押しされ、結束力が高まった。「支えてくれた多くの方に恩返し」を合言葉にプレーオフを勝ち上がり、最終的に大分は見事にJ1昇格を手にしている。
しかし、ここからは苦難の連続だった。経営再建中のクラブにとって、財政面が安定していないため、チームも戦力が整わず、成長過程の段階でJ1に復帰したことは誤算だった。強化費は前年から2億円弱を上乗せして4.5億円となったが、J1リーグのチーム強化費の平均は約14億円であることを考えると、あまりに脆弱な予算だった。
強化費と順位は比例している。少なくともJ1では、力がなくても頑張ればどうにかなる、という考え方は通用しない。雑草軍団が努力を積み重ね、最終的に良い結果を出すというドラマは残念ながら生まれない。強いクラブには強い個がある。それにプラスαしてチーム力を高めている。チーム力で個の力を補えるという考えに限界があった。それは分かっていたことだが、実行できる財政力がなかったため、どうすることもできなかったのが事実だろう。
J2の6位から這い上がり、J1昇格を射止めた大分だったが、そのシーズンはわずか2勝しかできなかった。成す術なく6試合を残してJ2降格が決定した。だが、この年の降格に関してはある程度予測できていたことであり、サポーターも社長や監督に責任を取らせるような騒ぎがなかった。どちらかというと1年であったが、J1を経験できたことを喜び、ご褒美のような1年だったと、いまでも思う。
▼プレーオフは”一獲千金”の場
それでもJ1のステージで戦うことが大分のミッションであることは、誰もが信じて疑わなかった。2015年にJ3降格に至るまでは……。
なぜこのような状況に陥ってしまったのかーー。それは内部のゴタゴタがあったように思える。2011年からチームを指揮した田坂和昭元監督をシーズン途中に成績不振で監督解任に踏み切ったが、次期監督を見付けることができなかった。監督の諸条件を「Jクラブの監督経験者で、下部組織などで育成の経験がある人」に絞り、条件を満たす候補者数人と交渉したものの、話がまとまらず、強化部のトップが監督になるという事態が起きてしまった。
万が一のことを考えて水面下で奔走するのが、強化部長やGMの仕事だが、人材が抜けたときのリスクマネジメントを欠いていた。しっかりとした方向性がないまま監督を解任し、選手をかき集めても、中身がないから張りぼてのチームしか作れず、そのまま崩壊につながってしまった。強化の失敗は否めず、フロントの責任はやはり大きかった。
そして、大分の最大の魅力であった、大分愛を持った選手が少なくなったことは致命的だった。これまでチームに脈々と流れていた「ひたむきに仲間のため、チームのために走って戦うサッカー」ができなくなった。サッカーを根性論や感情的に語るつもりはないが、2015年は「チームのために」、「監督のために」といった発言をする選手があまりに少なかった。
選手たちがどこか他人事のように、淡々とプレーしていた。悪いプレーやミスに対して誰かが怒るわけでもなく、そこに危機感を感じる者もいなかった。誰も矢面に立たないし、立とうとしない。誰も責任を取ろうとしない。戦う気持ちが伝わってこなかったし、チームとしてバラバラな印象を受けた。
これまでなら宮沢正史、高木和道らキャプテンシーを発揮できる選手が、ピッチ外でチームをまとめていた。しかし、表面に現れない仕事をしていた功労者を評価することなく放出したツケがここに出た。それが誤算の原点だったようにも思う。リーダーなき後は、まとまりに欠け、いつしか一体感のある戦いでリーグを沸かせていた「トリニータらしさ」が抜け落ちてしまったのではないだろうか。
そして、これまでの反省を生かし、形となったのが今季だった。クラブOBの片野坂知宏氏を新監督に迎え、スタッフも強化部にもOBを据えた。”大分愛”に包まれ、チームも原点である”育成”に重きを置き、アカデミーや生え抜き選手を戦力になるまで育て上げた。長い時間をかけて構築したパスサッカーをベースに苦しみながらも、J3優勝、そして1年でのJ2昇格という最高の形でシーズンを締めくくっている。
来季はJ2での戦いとなる。当面はJ2定着が目標だ。帰るべき場所はJ1ではあったのは過去のこと。現実を見据えると、J1昇格は奇跡的にプレーオフに勝つしか方法はないのではないか。自動昇格の2位以内を狙えるチームになるまでには時間が必要だ。
たとえ、チームがプレーオフを勝ち抜きJ1に昇格しても、1年で降格するのは目に見えている。ただ、それでもいいのではないか。ご褒美に1年間のJ1生活を楽しみ、またJ2で力を付ける。それが5年に1回、10年に1回でもいい。その繰り返しを楽しむクラブであってもいいと思う。プレーオフは弱者が一攫千金を狙える夢売るシステムーー。私はそう思う。
柚野 真也(ゆの・しんや)
1974年生まれ。大分市出身。2002年のサッカー日韓W杯を機に、スポーツの持つ”吸引力”に引き込まれ、フリーの編集者・ライターに。プロからアマチュアまで地方のクラブ、有名無名問わず名もなきアスリートの歓喜と悲哀を言葉で綴っている。