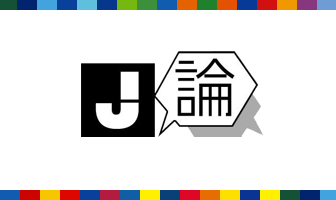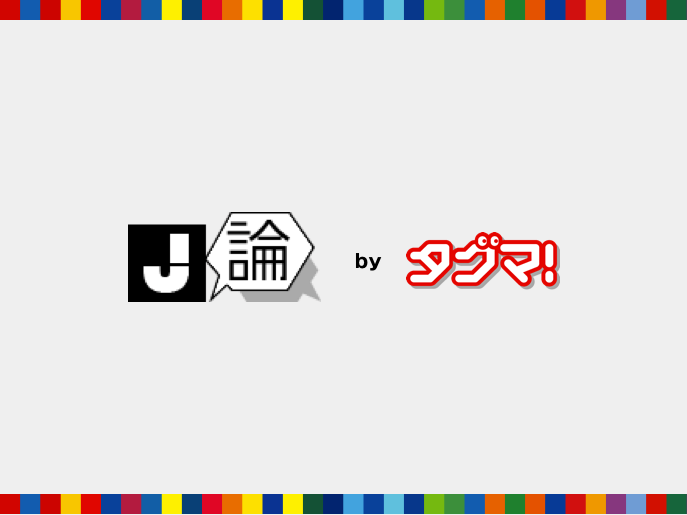ささやかな誇りと共に、松本の番記者が丹念に追い続けた十年を振り返る
松本山雅の番記者として、チームを一心不乱に追い続けてきた男、多岐太宿に語ってもらった。
▼偶然の成り行きで山雅番に
平成26年11月1日、レベルファイブスタジアム――。
松本山雅FCはこの日、アビスパ福岡に2-1で勝利。この結果、今季のJ2リーグ2位が確定。晴れて来季はJ1へ舞台を移すことがほぼ確実となった。
この歴史的一日を記録すべく、長野県内はもちろん全国から多くのメディア関係者が福岡へ駆けつけていた。筆者もその一人だが、その場にいてなお、実感が沸いてこない。それが正直な感想だ。リーグ戦はまだ3試合も残っており、それが終われば、あらためて感慨に耽るのだろうか?
そもそも筆者が松本山雅をウォッチするようになったのは、2004年だった。当時の筆者は文筆を生業にすべく、地元新聞数社の面接を受けるも全敗。世間の厳しさを感じつつも、文筆で稼ぐことをあきらめきれずに自称ライターとして活動をスタートさせていたところだった。
ちょうどその頃、山雅サッカークラブがJリーグへの加盟を目指して、新たな体制のもとでスタートを切った。地元のクラブがJリーグ昇格を目指すという”物語”――。書く側とすれば、これほど面白い対象はない。つまり、筆者と松本山雅とのファーストコンタクトはある意味で全くの偶然だったわけだ。
▼辛島山雅から吉澤山雅へ
2005年、名称を松本山雅FCに代え、心機一転。プロ監督として、G大阪などでプレーした辛島啓珠(現・佐川印刷京都監督)を招聘。実はこの招聘にも二転三転あり、Jリーグクラブで指揮を執っていたあるビッグネームの名前も挙がっていたという。諸事情あってその話は流れたが、結果的に野心ある青年監督とのタッグはクラブにとって僥倖に違いなかった。
カテゴリーは異なるとはいえ、3シーズンを指揮して優勝2回、2位が1回。当時の北信越リーグ1部は全8チーム。ホーム&アウェイのリーグ戦は14試合しかなかった。短期決戦、しかもライバルチームはAC長野パルセイロ、ツエーゲン金沢、JAPANサッカーカレッジと難敵揃いである。そういう中で手駒を駆使して結果を出してきた辛島監督の手腕は、あらためて認められるべきだろう。
それでもJFLへの壁は厚かった。2007年、地域リーグ決勝大会(JFL昇格を決めるプレーオフ)で敗退した辛島監督は退任。後任はHonda FCでJFL優勝経験を持つ吉澤英生(現・鳥取U-18)監督だった。
この吉澤体制の3年半、振り返れば実にドラマティックだった。天皇杯で湘南、浦和に勝ち、JFL昇格も成し遂げた。しかし、どうしても足踏みを続けたという苦い味の方が強く記憶に残っている。2008年、2009年ともにリーグ戦は4位で終了。2011年も低空飛行のまま解任の憂き目にあった。その意味で吉澤監督の評価は毀誉褒貶ある(名誉のために記せば、前述のように多くの栄光をクラブにもたらしている)。
ちょうどこの頃から、「夏場過ぎから本気出す」という体質が”山雅劇場”と表現されるようになってきた。それは裏を返せば「夏過ぎるまで本気出さないよ」ということで、あまり褒め言葉ではないのかも知れないが……。この当時は、筆者は働きながらの兼業ライターだった。物書きで生活するのは夢のまた夢であったが、クラブ公式や地元誌・フリーペーパーに少しずつ文章を書くようになっていた。
▼ささやかな誇りと共に
2011年に松田直樹が加入し、クラブの知名度は一気に上がった。この年の元旦、筆者は明治神宮で「サカマガ、サカダイ、スポナビ、エルゴラ、そのどれかでいいので原稿を書きたい!」と祈願してきた。結果的にその4媒体すべてに寄稿するようになるのだが、そのたびに8月の”あのこと”を書かなければいけないのは正直つらかった。それでも、依頼があった以上、書くことが務めだと思い直した。あのとき、ちょうど今のように全国のメディアでクラブ周辺は蜂の巣をつついたような騒ぎだった。「全国のメディアから、クラブを取り返せ」ということを知人のサポーターから叱咤された記憶がある。そんな大それたことをできる能力はないが、だからこそ、松本山雅の戦いをきっちり追いかけて行こうと心に決めた。宮崎の地でJ2昇格を決めた試合も、現地に飛んだ。振り返れば、北信越リーグ1部、JFL、J2、そしてJ1への昇格を決めた全ての試合において筆者は現地にいた。それはささやかな誇りだ。
そして、反町康治監督の指揮の下、J2で3年間。2012年から専業になった筆者も、クラブがこれだけ速く成長するとは予想もしていなかった。就任当初の2012年はサポーターにはお馴染みの喫煙問題などもあったが、あれは喫煙の是非よりもチームを一つの方向にまとめるための”踏み絵”の側面が強かった、と筆者は考える。
たとえば小松憲太を多くの試合で起用した理由について指揮官は「あいつよりも上手い選手は他にもいたが、チームのために頑張れる選手があの時のチームには必要だった」と振り返っており、何よりもチームを一つにまとめ、同じベクトルを向かせることに重きを置いていたことが分かる。そこからの快進撃は、御存知のとおり。今季は夏まで沈む”山雅劇場”はなかったが、大海を知り尽くした船長が正しい航海図のもとに出航すれば、誰も迷うことはないという証左だ。
地域リーグ2部からJ1へ。10年に渡る、松本山雅のオデッセイ――。
そのあまりにも濃密な時間は、選手・スタッフ・サポーターなど多くの人間によって支えられてきたのだとあらためて思う。その歴史の証人がいる限り、物語はこの先も色あせることなく時の流れに耐えていくだろう。
多岐太宿
大島和人(党首)世代の雑食性ライター。生まれも育ちも信州の片田舎。高校卒業後、社会の歯車として労働に勤しむ傍ら、地域リーグ時代から地元の松本山雅FCをウォッチ。地元紙やサッカー媒体に原稿を執筆し、12年3月より専業ライターとして独立。『J’sGOAL』『エル・ゴラッソ』『月刊J2マガジン』などで担当を務めている。県内の他スポーツやグルメなど地域情報の執筆も手掛けており、そっちが本職(多分。しかし微妙)。