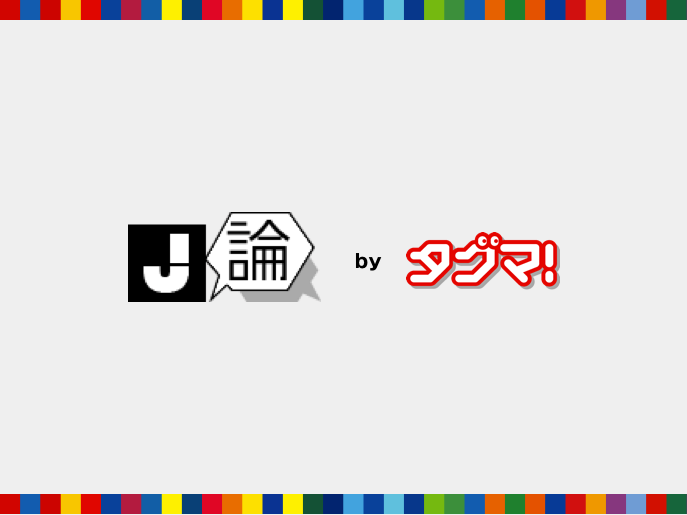連覇の広島番記者が読み解くJリーグ後半戦。果たして「広島の時代」は終わったのか?
3連覇を狙う王者・広島を追い続ける情熱の番記者・中野和也。感じるのは交代の予兆。「自分たちのサッカー」は勝てない時代なのか?
▼3連覇を推すのは難しい
今、Jリーグは歴史の大きな転換点の中にある。
広島は史上4クラブ目となる連覇を、J1財政規模平均が平均以下となる地方クラブが成し遂げた実績は、「奇跡」などという表現すら過小評価に聞こえる。たとえその快挙の価値が理解できない人々に「面白くない」と批判され、相手の守備的な戦術ですら広島の責任を問われたにしても、それもまた「勝ったからこその理不尽さ」とも受け止める。それほど「勝利」の味は甘美であり、優しい。
だが今季、ACLとの並行日程はやはり厳しかった。チームとして深いダメージを負ったのは否めない。富士ゼロックス・スーパーカップでは、天皇杯で口を極めて広島を批判したジャーナリストも評価せざるを得ないほどのサッカーを見せ付け、第1節のC大阪戦、第2節の川崎F戦も共に1点差ではあったが、内容の伴った勝利を手にした。「広島の時代」はまだ続くと思われた。
だが、疲労は選手たちの肉体と頭脳を蝕み、チーム練習もできない過密日程は連動性と連係をさび付かせる。14試合を終えて勝ち点『22』は昨季同時期より5ポイント減。23得点は17得点に落ち込み、シュート数やチャンスの数も昨年よりも目に見えて減少した。
再開初戦となった7月15日の横浜FM戦、広島は自陣に引いて守備を固めた相手に対し、何度かクサビは打ち込むものの、有効な連動性は生まれない。「3人目の動き」がないからフリックもチャンスにつながらず、守備的な横浜FMの術中にハマってしまった。後半は柏好文や山岸智の突破で打開を図るが、クロスが中で合わない。たまたま、こぼれ球が石原直樹の足元に落ちたことでゴールにはつながったが、その後もチャンスは作っているものの、決定的と言えるほどの場面は訪れない。
この試合、交代で入った野津田岳人やファン・ソッコも機能せず、前でキープできなかった広島は、試合終了間際に逆転を許して完敗。だが問題は「守り切れなかった」ことではなく「攻められなかった」ことにある。室蘭キャンプでやってきたことが、ほとんどできなかった。後ろから数的優位を作ることもなく、連動性も失ったままだとしたら、「広島の3連覇」を予想するのは難しい。
▼機能し始めた「広島対策」
広島の攻撃の特長は、特に後ろでパスを回しながら相手を呼び込み、スペースをつくった上で一気に攻撃を仕掛ける戦術である。だがもはや、広島に対して「前から追う」チームは、ほとんどなくなった。もちろん、局面ではプレッシングを受けるシーンもあるが、広島が自分たちのスタイルを貫いて連覇という偉業を達成したことで、「広島を潰すこと」を主眼とし、時にゲームを壊してもいいくらいの割り切りを見せるチームがほとんどだ。「ボールをほとんど広島に持たれていたけれど、それも一つの考え方。ストッパーも含めて巧い選手が多いし、しっかりとブロックをつくって我慢することも大事だから」と中村俊輔(横浜FM)は語っている。「最後は(栗原)勇蔵がロングボールにチョンと触ってのゴールになったりする。形以上に何かがあるというのは、大きいね」とも。
これまでの成功体験そのままでは通じない状況に、王者は陥っている。森保一監督は横浜FM戦後、「相手の我々に対する対策はこれまで以上。その上をいく気持ちとモチベーションをあげていかないと、簡単に攻撃はさせてくれない」と語った。ミハイロ・ペトロヴィッチ前監督が率いる浦和ですら、広島にはほぼ完全マンマークで潰しにかかる。かつてその戦術について槙野智章は「あまりに消耗が激しい。広島戦だからこそ、チャレンジする」と語っていた。実際、広島戦直後の浦和の戦績は芳しくない(広島対策を講じた2012年後半以降は1勝3敗 ※今季はナビスコカップ)。それでも、彼らは広島を潰すことを優先している。それが、栄冠に近づくための最短距離と認識しているからだ。
▼「スタイルを貫く」ことが批判される時代に
フットボールやJリーグの未来を考えたとき、それでいいのかという気持ちになることは確かである。ただ、今やオランダですら、現実的な対策を講じる時代だ。「相手を潰す」ことで「自分たちもサバイバルできる」ことが、「自分たちのサッカー」の追求よりも先んじる――。
最近、日本代表敗戦の影響で、「自分たちのサッカー」と言葉にすることすら憚(はばか)る雰囲気が出てきてしまった。理想を捨て現実に走ることが正しい。サッカー解説者ですら、そんな言葉を口にする。4年前、スペインが優勝した時はあれほど「スタイルを貫く」ことの正しさを賞賛していたというのに……。
そんな今日のJリーグにおいて、自らのスタイルを堅持し、自信を持って表現しているのは、川崎Fだ。広島とは違った形でのポゼッションサッカーを構築して相手を圧倒するだけでなく、得点源が大久保嘉人・小林悠・レナトと複数存在することも彼らの強みだ。今季はまだレナトにキレは見られていないが、昨季12得点をあげた彼のパフォーマンスが上がってくれば、川崎Fの攻撃は止められないだろう。チームで崩すだけでなく、個人での突破も可能なチームだけに、広島よりも対策を立てるのは難しい。
広島と川崎Fの試合は、多くの場合、互いが攻め合う戦いとなる。スタイルvsスタイルの対決は、切るか切られるかのスリリングなシーンが満載だ。これぞエンターテインメントだとも思うのだが、そんな気概は「降格」「優勝」という現実の前には無意味である。「勝たなければ意味がない」という感覚は、降格も優勝も味わった広島と共に歩いていれば、実感として胸にくるものがある。だが一方で、「潰し」「潰される」ということのみに特化した戦いにカタルシスは存在するのだろうか。そんな疑問も少なからずあるのだ。
広島対横浜FM戦の前半を「猪木・アリ状態」と評したが、そんな状態が続くと未来は暗澹としたものに思えてくる。だが現場は、そんな感慨に浸る暇もない。広島も横浜FMも、中3日の日程で次の試合への準備を整えないといけない。現実と向き合わないといけない。理想を追いかけ、届かずに挫折した2007年の教訓は、今も広島の中に脈打っている。だからといって、現実とだけ向き合って戦う日々がいかにむなしいか……。それもまた、ペトロヴィッチ就任以前の歴史が、物語っている。
▼そして、時代は巡る
冒頭に「歴史の転換点」と書いたが、それは歴史を彩ってきたベテランと未来を担う若者たちとの戦いが、本格的に始まる時期が来たということだ。横浜FMは未だに中村俊輔の時代だし、川崎Fも中村憲剛と大久保のチームである。だが、いつまでもそれで、いいのだろうか。若くて可能性のある選手が海外にすぐ飛び出してしまう事情もある。柿谷曜一朗も結局はJリーグを去り、山口蛍もC大阪のシャツを脱ぐ日も近いのかもしれない。だが、だからといって、Jリーグがベテランたちにとってずっと居心地のいい場所であっていいはずはない。
今季、浦和を牽引しているのは、阿部勇樹ではない。柏木陽介だ。神戸は確かにブラジル人選手たちが得点を重ねているが、彼らを操っているのは22歳の森岡亮太である。鹿島は、小笠原満男から柴﨑岳への「禅譲」が始まっている。
広島は、どうなのか。佐藤寿人という偉大なストライカーの後を引き継ぐたくましい若者が、果たして登場するのか否か。候補はいる。キャンプ中の練習試合で3試合9得点を叩き込んだ大卒ルーキーの皆川佑介か、U-21日本代表の野津田岳人、あるいは浅野拓磨か、U-19日本代表の川辺駿も候補だろう。森保監督は情熱的で勝利への想いがほとばしっている指揮官だが、一方で先も見ている。新旧交代への深謀遠慮は存在すると見る。
「今、負けた者が明日は勝利者になる。時代は変わるんだ」とボブ・ディランは言う。平家物語は「祇園精舎の鐘の音、諸行無常の響きあり」と語り、全ての事象は姿も本質も常に変化すると伝えている。
広島の時代も、Jリーグ自体も、おそらく変わっていくのだろう。だが、それを恐れてはならないのではないか。吉田拓郎が語ったように「古い船を動かすのは古い水夫ではない」のだ。新しい海にこぎ出すのは、海の怖さを十分に知り尽くしている古い水夫ではなく、野心に富んだ新しい水夫の方が適している場合もある。
日本サッカーと各クラブにとっての「新しい水夫」が果たして誰なのか。J1リーグ後半戦。現実の戦いを楽しみながら、そんな希望を探してみたいと思う。
中野和也(なかの・かずや)
1962年3月9日生まれ。長崎県出身。居酒屋・リクルート勤務を経て、1994年からフリーライター。1995年から他の仕事の傍らで広島の取材を始め、1999年からは広島の取材に専念。翌年にはサンフレッチェ専門誌『紫熊倶楽部』を創刊。1999年以降、広島公式戦651試合連続帯同取材を続けており、昨年末には『サンフレッチェ情熱史』(ソルメディア)を上梓。今回の連戦もすべて帯同して心身共に疲れ果てたが、なぜか体重は増えていた。