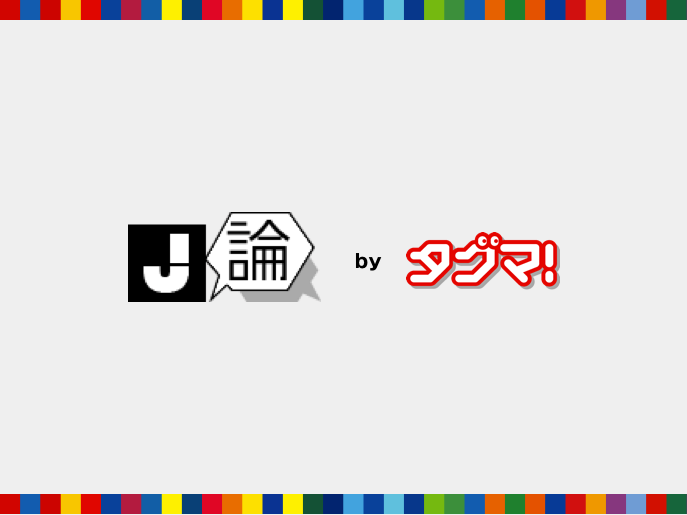なぜ浦和レッズは終盤に失速し、ペトロヴィッチ監督はまたもタイトルを逃したのか?
浦和レッズの番記者・神谷正明が急失速した赤い悪魔を語り尽くす。
▼レッドカードを3枚もらえるか?
またしても届かなかった。浦和は最終節で名古屋に1-2で敗れた。得失点差で首位に立っていたガンバ大阪が徳島ヴォルティスとスコアレスドローに終わっただけに、もし名古屋グランパスに勝っていれば、8年ぶりのリーグ制覇となったが、結果は逆転負け。虚しい形で自らその権利を放棄してしまった。
これで優勝争いに加わりながら力尽きるというのを3年連続繰り返すことになったが、今年のチームは過去2年の自分たちとは違うというところを見せていた。特に精神面の成熟ぶりは著しいものがあった。
それまでは気持ちよくプレーしている時は輝いても、うまくいかなくなるとあっさりとつまずいてしまう幼いチームだったが、今年は苦しい時こそ選手たちの眼がギラギラするようなチームだった。うまくいかなくても我慢する、球際の攻防で躊躇しない、地べたを這いずり回ってでも相手を止める。気迫と執念で劣勢を跳ね返そうとするたくましさを身に付けてはいた。
浦和は過去2年に比べると、はるかに戦えるチームになっていたのだ。
だが、それでも最後にナイーブな姿を見せてしまった。試合後、ミハイロ・ペトロヴィッチ監督は今シーズンの選手たちの奮闘を称え、「彼らは批判されるべきではない」と話す一方で、課題についても触れた。
「日本人選手の中で、もっとこうしたほうがいいと私が思う部分で言えば、毎試合毎試合が同じ戦いではないということです。たとえば優勝や降格など、何かがかかっている戦いの中で、選手たちがレッドカードをもらってでも勝ち切るというメンタルの強さ、そういう試合での勝ち方という部分については、もう少し改善できる部分があると思います」
「勝つためであるならば、たとえ退場をしてでもチームは勝ち切らなくてはいけない、それくらいのメンタリティーを持ってやらなくてはいけないのですが、何かが懸かった試合のなかで、どう選手たちが戦うのかという部分で、日本人選手はもっと意識を変えていく必要があると思います。たとえば試合前のミーティングで、絶対に勝たないといけない、たとえば『レッドカードを3枚もらってでも勝たないといけない』と私が言ったら、選手たちはおそらく何を言っているのかと思うのかもしれません。そういう部分で言えば、ヨーロッパなら3試合前に勝点5をリードしているチームであれば、もっとハードな戦いをするのではないかと思います」
▼指揮官の采配にも問題あり
勝負に徹するメンタリティー、判断力と決断力。状況に応じて戦う術を身につけ、望む結果を出すために最善の選択ができるようになること。そういった面がまだ足りないと指揮官の目には映った。その指摘は間違っていない。そういった部分は今シーズン大きく伸びた部分だが、それでも詰めの甘さが目立つ試合はいくつかあった。
ただ、その指摘は指揮官自身にも当てはまることだ。
たとえば、G大阪戦がそうだった。首位と2位の直接対決であり、リーグタイトルの行方がかかる天王山ではあったが、あの時点で浦和とG大阪には勝ち点『5』の差があった。必然、G大阪は必勝態勢で臨まなければいけない試合で、逆に浦和は引き分けでも十分な結果だった。両者の激突は膠着状態が長く続いたが、それで困るのはG大阪のほうである。浦和は0-0でも悪くないが、G大阪はそれでは実質的に”終戦”だ。
しかし、先に動いたのはG大阪ではなく、浦和のベンチだった。
まず56分に早くも一枚目の交代カードを切っている。梅崎司を下げ、マルシオ・リシャルデスを投入した。この日の梅崎の出来は特段に悪かったわけではない。”いつもと同じ”膠着状況を打破しようとする采配だ。そしてその8分後には平川忠亮に代え、関根貴大を送り出している。平川は攻守のバランスに優れたタイプだが、関根は守備に課題を抱えるものの、ドリブル突破という強力な武器がある。これも”いつもと同じ”攻撃的にいくという明確なメッセージが込められた交代策だ。
ちなみに、G大阪が初めて交代のカードを切ったのは、71分だった。
指揮官があれだけ明確なメッセージを送れば、選手たちのマインドが攻撃へと傾くのは当然だ。浦和は88分に失点を喫することになるが、FKからカウンターを受けたのが要因だった。引き分けでもOKという意識を持っていれば、まずやられるはずのない形である。このときはリシャルデス、関根、宇賀神友弥の3人がカウンターに備えていたが、いずれも守備に特長のある選手ではない。失点の場面で「運がなかった」のは確かだが、付け入るスキをわざわざ与えていたことも、また事実だ。
勝って優勝を決めたいというペトロヴィッチ監督の心境は理解できる。しかし、最大の目的はあくまで優勝であって、G大阪戦での勝利ではない。あの時点では「残り3試合で優勝」を考えればよかったが、指揮官は「G大阪に勝って優勝」というシナリオしか見ていなかった。
それが最後の交代、つまり興梠慎三の投入という無謀な一手にもつながった。鹿島戦で腓骨骨折していた興梠はG大阪戦の2日前、「ちょっと痛い状態でピッチに立ってもチームに迷惑をかける」と話していた。骨はくっついているのかという質問に対し、言葉を濁す場面もあった。回復はしてきていても完治はしていないというのが伝わってくるやり取りだった。そんな状態の興梠をピッチに送り出すのはあまりにリスクが高い選択であり、実際、興梠はたった数分のプレーで故障を悪化させてしまった。
3試合で優勝することを念頭に置いていたとしたら、選択肢には入らない交代策だっただろう。あと1週間休ませれば、鳥栖戦ではプレーできたかもしれないし、仮に鳥栖戦がダメでも最後の名古屋戦に間に合う可能性はあった。仮に間に合わなかったとしても、あの時点では残り2試合に希望を残すというのが普通の考えだろう。G大阪に負けても優勝の可能性が消えるわけではなかったのだから。終了間際にリードを奪われて敗戦濃厚の展開のなか、治りかけの選手を投入するというのはあまりに無茶な賭けだった。
▼勝ち方を学び。身に付ける
リスクが高過ぎる采配は最終節・名古屋戦でも見られた。
指揮官は1-1の同点で迎えた86分に鈴木啓太を投入している。鈴木は不整脈でその前の2試合を欠場していた選手だ。練習には参加していたものの、実戦から離れれば試合勘は鈍るし、コンディションも落ちる。まして原因不明の病気に苦しんでいるのだから、調子がいいはずもない。
いくら百戦錬磨のベテランであっても、そういったマイナス要因を抱えたまま、しかも逆転優勝に向けて非常にテンションが高くなっている試合へ途中から入って仕事をするのは困難な作業だ。実際、鈴木は交代直後に縦パスをカットされ、カウンターから失点を喫する要因を作ってしまったが、その責任を彼ひとりに求めるのは酷な話だ。
ドクターからOKが出ていたからベンチ入りできたのだろうが、シーズン終了後に手術を受けることが発表されたことから考えても、不安を抱えた状態でのプレーだったはずだ。そういった選手をベンチに置かざるを得なかったこと、また興梠のケースでも言えることだが、万全の状態からほど遠い選手でも使わざるを得なかったというチームマネジメントには改善の余地があるだろう。
それは深い信頼の表れであると同時に、特定の選手しか頼りにできないということの証左でもある。浦和が他のチームに比べて選手層が薄いのかと言えば、そんなことはないだろう。主力偏重の采配を続けることで、レギュラー組と控え組の間に差が生まれてしまった。それは広島を率いている時から言われていた弱点でもある。
ペトロヴィッチ監督は優秀な指揮官だ。就任1年目に、前年に降格の危機に瀕するまで低迷していたチームを瞬く間に立て直し、優勝争いに加われるまでに成長させた。そして2年目も、3年目の今年もリーグタイトルを争える位置に導いた。
Jリーグは実力が拮抗しており、どこが優勝してもおかしくない、非常に競争の激しいリーグだ。優勝争いをしていたチームが翌年に降格することもあり得るし、その逆もまた然り。そして、監督交代がその浮き沈みの大きな原因になることも珍しくない。そういったリーグでペトロヴィッチ監督は就任してから毎年のように優勝争いをしているのだ。その事実が彼の能力の高さを証明している。ただ、日本に来てからの8年でタイトルを取れていないというのも、また事実だ。勝つために改善していかなければいけない部分があるということだ。
悲願のタイトルを勝ち取るためには、選手たちと一緒に指揮官も成長し、勝ち方を身に付けることが求められる。強烈な痛みとして残った今年の教訓を糧にして、チームとしてもう一皮むけた姿を見せてほしい。彼らなら、さらなる高みに到達できると信じている。
神谷正明(かみや・まさあき)
1976年東京都出身。スポーツ専門のIT企業でサッカーの種々業務に従事し、ドイツW杯直前の2006年5月にフリーランスとして独立。現在は浦和レッズ、日本代表を継続的に取材しつつ、スポーツ翻訳にも携わる。