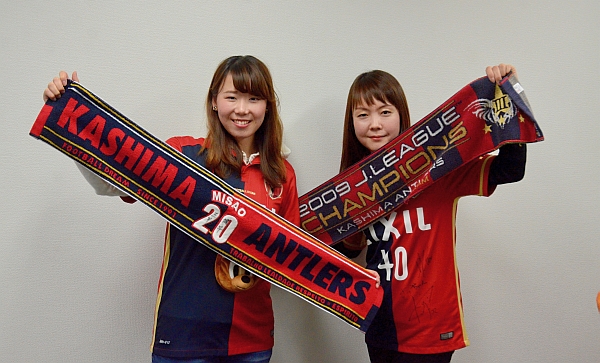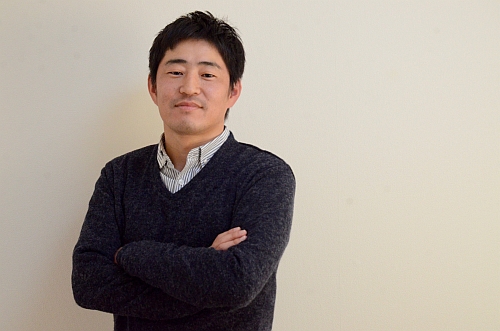
「この仕事は小さな仕事を決して疎かにせず、そこに自分のすべてを懸けてできるか。それ以上でもそれ以下でもありません」鈴木康浩【オレたちのライター道】
熱量や愛情といったものがあった上で書くモノには絶対に力が宿るんですよ
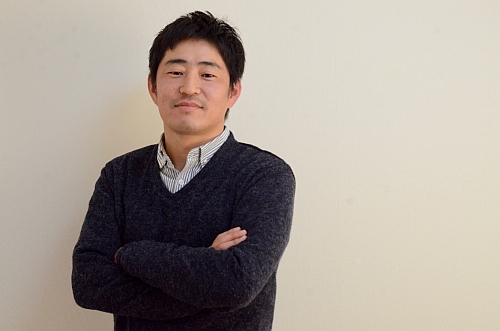
▼公務員からパティシエ修業へ
――まずは経歴から聞かせてください。いわゆる新卒としては、どんな仕事を始められたのですか?
僕は適当な大学生活を送っていたのですが、ボンヤリと、ずっと続けてきたサッカーをやる時間だけは作りたいなあと思い、それならば公務員かなあと思ったんです。それで大学を卒業したあと実家のある栃木で国家公務員の勉強をして、卒業をした次の年に国家公務員二種に合格しました。10月1日からの採用でお金もなかったので、早めに働きたいと10月1日から働き始めましたが、地元の国家公務員と言っても、地方にあるのは国立大学など限られていたため、宇都宮大学の職員として採用されました。
仕事の内容は主に事務仕事。人事課に配属されたので、大学の教授の年俸も把握できたため、事務職員との初任給の違いに愕然としましたね。やはり人間、あまりにも時間があり過ぎると、余計なことを考えてしまうものです(笑)。
――たしかに公務員は時間が余りそうなイメージです。
若い人特有の「オレ、この人生でいいのかな?」とか余計なことを考えていました。サッカーをプレーする時間を削がれたくないという思いで選んだ職業だったので、別にしがみつく必要もないかなと考えていました。
「どうしようかな?」と考える中で時が経ち、「自分はこのままでいいのかな。そうだ、いわゆる自分探しをしよう!」と24歳ぐらいのときに、大学のときに受けた『職業適性検査』を押し入れからひっぱり出してみたんです。。直感で400問ぐらいの質問を答えていく職業適性検査で各職業の偏差値が出るのですが、映画監督や編集者・ライターといった職業の偏差値が65くらい。そのなかで一つだけ飛び抜けて偏差値が75と高い職業がありました。それがなんと『パティシエ』だったのです。
――スウィーツをつくる職人・パティシエですか。
自分は手作業を軸とした”職人”と言われる仕事に昔から憧れていたこともあって、パティシエも職人なので、「いいかも。とりあえずやってみるか」と思い立ち、実家の宇都宮から代官山にある一流の某専門学校に入学しました。その専門学校には土曜日だけ講義がある社会人学校のようなものがあって、3時間3コマ、1日計9時間の講習や実技を受けました。
そして自分に合っているかどうかを見極めていく中で、「本物のパティシエになるのならば、フランスに行く必要があるだろうし、フランスでサッカーが見られるからいいな。細かい手作業も自分に向いていたし、さすが適性検査。自分にピッタリだな(笑)」と思い始めて、半年間続けました。
でも、その中で「ケーキの道を極めようとすると、サッカーから離れるな。やっぱり違うな」と思い始めたんです。自分でやってみて始めて選択肢が消えるということを実感しましたね。オレは職人をやりたい、でもサッカーは離れたくないと考えている中で、二つをくっ付けたら何があるのかと考えたら、サッカーライターという仕事が浮かび上がってきました。原稿を書くのは比較的得意だったんです。
――その後はサッカーライターを志望されたのですね。
もうすでに自分は社会人ですが、何かないかなとインターネットで探している過程で、のちに自分が入る事務所で『サッカーライター新人賞』に応募することになったんです。公務員の仕事を続けて食いぶちを稼ぎながら、週末はサッカーをプレーして、自分が所属している栃木県リーグ3部のチームで起きている出来事をまとめる原稿を書き始めました。
そのチームは年齢層も結構高く、下手をすればすぐに消滅してしまいそうな危ういチームでした。若い選手をなんとか口説いてチームに引き留めたり、その危うさや一生懸命さなどの人間味のあるドラマが面白くて、ピッチ内外のことを自分目線で書いていました。いざ、その内容で応募をしたところ、『サッカーライター新人賞』の頂点までたどり着き、新人賞に協賛してくださっていた講談社の方から賞とともにお褒めの言葉をいただきました。その結果、これはイケるなと……(笑)。
――公務員の仕事はどうされたのですか?
公務員は結局4年間で辞めました。公務員を務めながらもいろいろなことを同時並行でやって、サッカーライター賞をいただいた事務所では2週間に一度実施されていた『スポーツライター講座』に通いながら勉強をさせていただきました。公務員を辞めてからはサッカーライター賞を主催していた作家の方と日々一緒に帯同させていただきながら、いろいろと勉強をしました。
その時期は、昼間は弁当配達の仕事をして、夕方の16時ぐらいからその事務所で仕事をして、また翌日の朝から弁当配達の仕事をするという生活サイクルが続いていたんですけど、徐々にこの世界に入ったという感じですね。
▼転機は栃木SCのJリーグ参入
――当時の日本サッカーを取り巻く環境はどんな時代でしたか?
ドイツW杯での惨敗の翌年、2007年です。
――ちょうど、スカパー!さんがJリーグ中継を始めた年ですね。
ドイツで日本代表が惨敗したのでサッカー関連の出版不況に入った年だったと記憶しています。ただ、当時の僕はサッカー界の状況について、全然気にしていませんでした。例えば、自分の志向として浦和の選手の誰々で書きたいといった発想はなく、職人に対する憧れがベースにあって、そのうえで単純に自分の強みであるサッカーをモチーフに文章を書く道を極めたかったんです。
「自分の強みは何だ?」と考えたときにずっとやってきたことがサッカーしかなく、その強みを生かして、モノを書くこと、自分を表現すること、それがサッカーライターという職業だっただけで、スター選手の声を取って、どうこうしたいということは一度も考えたことがなく、それは今でもありません。
――事務所の仕事を手伝う立場から、いわゆる原稿を書いてお金をいただく段階へと次第に移行していくと思いますが、そうなるきっかけは何でしたか?
一つはお手伝いをしていた事務所に来る仕事をしながら商業誌に書き始めたということですね。その一方で地元の栃木SCの取材も並行して始めていました。単純に観客席から試合を見て原稿を書くだけでは、平板な原稿になってしまい、面白くないので、監督や選手の声が聞きたいと、当時の栃木はJFLだったので、カメラを持って報道受付に行くと、取材で入れるので、取材をさせていただきました。その取材の成果を原稿にまとめて自分のブログにアップすると、読者が反応してくれて、その期待に応えようとこちらも面白がって原稿を書く、ということを繰り返していました。
また、取材の現場に行くと、ほかの記者仲間と仲が良くなりますよね? たまたま僕の高校の大先輩だった、ある新聞社の記者仲間の方には試合が終わったあと、食事に連れて行ってくれることがありました。そうこうしている間にその大先輩が栃木を離れる際に、鈴木くん、書かない? といった形でマッチデープログラムのコラムを僕が書かせていただくことになったんです。マッチデープログラムなので、売り物ではなく、商業媒体ではありませんでしたが、印刷物として人の目に触れるようになったのは、それが初めてだったと記憶しています。
個人的には最初の入り口さえつかめば、そのあとは自分の原稿が面白いかどうか、その原稿のクオリティーで仕事の幅が増えていくだけだと思っています。そこからは自分の力次第です。
――なるほど。たしかにそうですね。
あと一番大きな出来事は、2009年に栃木がJリーグに参入したことです。JFLからJリーグに参入すると、『エル・ゴラッソ』しかり、『サッカーマガジン』、『サッカーダイジェスト』、『J’sゴール』と、いわゆる番記者が必ず必要になります。ある日突然、サッカーマガジンの編集の方から、「鈴木さん、この原稿書けますか?」と打診が来ると、ライターの駆け出しである僕は、あの老舗のサッカーマガジンから電話が来たぞ……とビックリするではないですか。そうなれば当然、「やります!」と言いますよね(笑)。
当時は(勤務先の事務所がある)三鷹に住んでいましたが、栃木のホームゲームの時は宇都宮に帰って、栃木SCの取材をして、採点・寸評などを書きながら、少しずつお金になりました。そういったなだらかな形で、この業界に本格的に入っていきました。そうこうしているうちに例えばサッカーマガジンさんから「ここのこのページも書けますか?」とか、あるいは自分で「こういう記事が書けますよ!」と売り込んで需要があれば、仕事は自然と生まれますよね。

▼必ず訪れる勝負どころ
――栃木SCを中心に取材をしながら、フリーランスになったタイミングはいつですか?
完全なフリーランスになったタイミングは、栃木がJ2に参入してから2年ほど経った後ですね。
――フリーランスの基本的な仕事の軸は、栃木SCだったのでしょうか?
原稿を書いていたジャンルは、ほとんどサッカーでしたが、栃木SCだけではご飯を食べられないので、宇都宮の実家に避難させてもらいながら(笑)、ジュニア世代の育成の記事など、栃木SC以外のサッカーのことも書いていました。ある出版社がライターを募集していたので電話をして繋がりを作ったんですが、例えばジュニア世代の記事をお試しで4ページ書かせてもらって、そこで勝負をしかけることもありましたよ。
仕事の幅を広げる時には絶対に(勝負を)落としてはいけない原稿があります。その原稿で編集者を信用させるために、原稿のクオリティーと取材対象者としっかりコミュニケーションが取れることをアピールするんです。
編集者が帯同する現場では、編集者がライターのだいたいの力量を測ることができるので、そこで自分の力を全部見せて、編集者から合格点をいただければまた次の仕事が来ますし、合格点をいただけなければ、次の仕事は来ない。単純にそれだけの話です。その4ページに一生懸命、命を懸けると言っては大げさですが、そうすることで、その4ページから始まった出版社との付き合いが今では大きなモノになっています。
――ライターとしての”勝負どころ”はありますよね。
この仕事は”わらしべ長者”ではないですが、小さな仕事を決して疎かにせず、そこに自分のすべてを懸けてできるか。この世界はそれ以上でもそれ以下でもありません。いまはようやく結婚もして、子供も産まれました。まさか自分がフリーランスになって仕事を始めた時には、もう結婚はしないかなと思っていましたよ。31歳でフリーランスになって、その時の稼ぎようと言えば、同世代の一般的なサラリーマンに比べたら酷いものでしたから(苦笑)。
意外と言っては変ですが、一生懸命に仕事をしていたらそれなりになりましたから、この道もありだなと。この仕事は、稼ごうとすれば稼げる仕事ですからね。結婚ができるタイミングで、パッと結婚しました。僕の生き方を理解してくれている奥さんには本当に感謝しています。
▼若手ライターへのメッセージ
――現在はタグマ!で『栃木フットボールマガジン』を展開されています。鈴木さんが思う栃木SCの魅力を教えてください。
一つは、以前からJリーグを目指すという動機があったことで、栃木に関わる選手やクラブスタッフからのものすごい熱量がありましたから、それに惹かれました。僕個人としても地元のクラブを愛するといったサポーター的な感覚を持ち合わせていますので、取材をしていく中で、そのクラブに対する熱量や愛情といったものがあった上で書くモノには絶対に力が宿るんですよ。
例えばテレビで日本代表の試合を見て、香川(真司)がどうだったとか、本田(圭佑)がどうだったとか、あの選手のパフォーマンスが良くなかったということを客観的に見て、分析をすることが、僕個人としてはあまり好きではないですし、得意でもありません。そういった分析記事は、すごく頭の良い方や原稿に切れ味が出せる方がやればいいと思っています。そういった切り口で読者を喜ばせる力を持った方は、素晴らしいと僕は思っていますが、僕個人の方向性と志向とは異なります。
個人的に愛情がこもる対象を書いて、勝手に力が宿るモノを、栃木のサポーターや、あるいは栃木のサポーターではない、他クラブのサポーターの方が読んだ時に、喜んでもらえるようにしたいんです。そのためにも、取材対象に対して、自分がそれに愛情を持てるかどうか、それは一番大事なことだと思っています。それがなければ、繰り返しになりますが、乾いた、平板な原稿になってしまいがちだし、そういう原稿を書いていても仕方がないと個人的にはそう思っています。
――なるほど。合点がいく話が多いです。
喜怒哀楽が無条件に湧き出てくるような対象を取材して書いた原稿は、絶対的なパワーを持つんですよ。職人もそうだと思いますが、それがモノ作りの原点ですし、一番大事なことだと思います。それができる僕にとっての取材対象が栃木SCなんです。栃木SCに対して愛情を持って取材をしていると、もともと持っている喜怒哀楽を軸にして、それを別のチームやクラブの取材対象者に向けることもできます。喜怒哀楽の感情を持って取材対象者にぶつかっていくと、相手にも喜怒哀楽がありますから、そのはね返りは何倍ものエネルギーに増幅して戻ってきます。そういうことを体感することが面白いではないですか。ですから、あくまでも自分の中の軸は持っていたほうがいいと思います。
今後サッカーライターを目指す方は、何かしら自分の軸を持っていたほうがいいと思います。自分の強みや喜怒哀楽といった感情のベースがないと良い原稿は書けないと、個人的にはそう思っています。
――同感です。
一言に集約すると、取材の強烈な動機です。取材の強烈な動機がないといい原稿は書けないですよ。例えば、ファジアーノ岡山の木村正明社長へ会いに行って、「素晴らしいですね。平均観客動員1万人をどうやって集めたのですか?」と聞くことは誰でもできますが、そこに元となる喜怒哀楽というバックグラウンドがあると、原稿が瑞々しくなると思うんです。僕の場合、それが栃木SCなんです。栃木SCというチームやクラブに対する強烈な喜怒哀楽があるから、それを軸にして岡山という他クラブにぶつけることができる。そうするとそれが岡山のサポーターにも響く原稿になるんです。これを僕が言うのもおこがましいのですが、若くしてサッカーライターの世界に飛び込んだ方は、たまに喜怒哀楽の軸になる部分がないような方もいると感じるので、あらためて考えたほうがいいと思いますね。
読者の心に響く、読者の心を動かすといったことは、書き手が喜怒哀楽の部分をしっかりと持っていないといけなくて、いくら説明的な文章を書いても人の心は動かないと個人的には思います。もちろん、説明的な文章でも『あぁ、なるほどね。うん、うん』と読者を”納得”はさせられるんですよ。ただ、その先を一歩超えた、読者の”心の扉”をバッと開けたり、そのパワーを持つためには、書き手の喜怒哀楽やものすごい感情のパワーがないと、読者の”心の扉”は開けられないと、僕はいつも思っています。
――僕も生意気ながら、後輩の記者と接する中で同じことを感じています。
原稿に喜怒哀楽が宿っているのか。そういう視点で僕の原稿を今一度読み返されると恥ずかしいんですけどね(笑)。「そんなことねえじゃねえか」という指摘もあるでしょうから……。
――そのほかに大事にすべきことはありますか?
やっぱり謙虚であることも大事だと思います。サッカーライターとして原稿を書けることは偉くも何ともないですし、その上から目線はすぐに読者も勘付くと思います。謙虚に、という視点で言えば、僕は栃木SCのサポーター気質のような部分も多少あると思っています。その部分も大事にしながら、一方で、客観的な証拠を集めた上で感情に流されずに何かを提示することは、日々栃木SCについて書く時には意識していることです。決して上から目線ではなく、足を使って地道に取材を重ねて、そして謙虚に書くということをやらないと、読者の心に響くような原稿は書けないんじゃないかなと思っています。
(後編「50歳ぐらいまでに自分の明確なスタイルを作り上げること。これは自分自身がやれるかどうかの勝負になります」鈴木康浩)
鈴木 康浩(すずき・やすひろ)
今年4月、栃木フットボールマガジンを円滑に軌道に乗せるために浦和のマンションを引き払い、故郷・栃木に戻った。現在は大自然のなかの伸び伸びした生活に心洗われる最高の毎日を過ごしている。これで栃木SCが来季J2に復帰できれば文句なし。
郡司聡
茶髪の30代後半編集者・ライター。広告代理店、編集プロダクション、サッカー専門新聞『エル・ゴラッソ』編集部勤務を経て、現在はフリーの編集者・ライターとして活動中。2015年3月、FC町田ゼルビアを中心としたWebマガジン『町田日和』を立ち上げた。マイフェイバリットチームは、1995年から1996年途中までの”ベンゲル・グランパス”。